1956年の最後の引き揚げ船1025人中、1人だけ帰国を拒んだのが彼女でした。収容所群の中でも“囚人の墓場”と呼ばれたマガダンで受刑者として9年間服役し、その後、地元官舎の守衛として生計を立て、そのままソ連人になった。生前の彼女は常々日本を突っぱねる言葉を吐いていたけど、最期に「早く帰りたかった」と涙したという話を聞きました。
当時の看護婦さんは一見花形の存在だったけど、彼女の場合、元は貧しい一家を支えるため20歳前後で朝鮮半島へ娼妓として売られた娘さんだった。戦後はソ連将校の相手もしたかもしれない。娼妓という別の世界に落ちてしまった、故郷に帰れる人間じゃないと自ら身を引いたんだと思いますね。
そんな彼女の運命には、近代から現代にかけての日本社会と女性というテーマに通じる問題が込められていると思います。彼女が生きていた証しを届けたかった。
時代が違えば全然違う生き方をしていた
──晩年を知る現地の人たちからはとても愛されていたようですね。正しいロシア語ではなくても、ののしり言葉だけは饒舌だったとか。
強い人だから言われたら言い返す。みんな懐かしそうに話してくれるんです。それだけ魅力のある人で、時代が違えば全然違う生き方をしていたかもしれません。私は秋田出身なのですが、1930年代の恐慌時、東北の子供がはだしで大根かじってる姿や「娘売ります」って札の写真を日本史の教科書で見ると、もし同じ時代を生きてたら秋子さんの人生は決してひとごとじゃなかった、と思いもしました。
──本の中の、「記録されなかった事実がいかに忘れ去られてしまうものか痛感する」という小柳さんの言葉は重いですね。
この本で伝えたことはささやかな事実だと思うんです。女性抑留者は本当に小さな存在でした。公式記録からこぼれ落ちた人たちで、何か大きな事件があったわけでも、彼女たちが何かを成し遂げたわけでもない。けど少なくとも、男性たちが経験したシベリア抑留とはちょっと違う見方を教えてくれた。どんなに過酷な環境でも生きがいを持って生きることができるという、人間の強さ、けなげさ、たくましさ。それさえ伝われば意味があったのかな、記録として。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

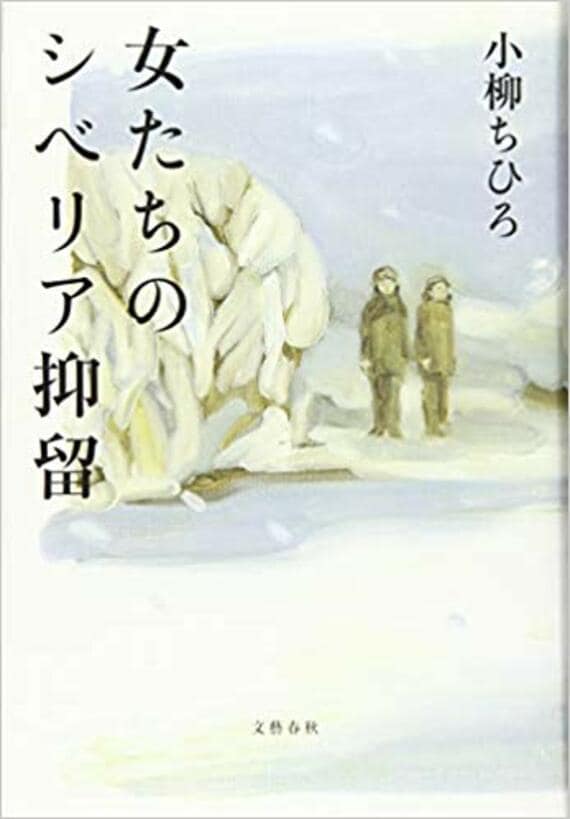






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら