プロ野球界の”リストラ”を描き続けた男 菊野浩樹プロデューサーが番組に込める思い
華やかな世界のプロ野球にあって、なぜ、菊野は土俵際に追い込まれた男たちばかりを追いかけるのだろうか。
「へそ曲がりってことはないんですけどね(笑)。バックストーリーのある選手のほうが、僕の感情に訴えてきます。たとえば挫折を味わっているとき、人間の本質や『負けてたまるか』という気持ち、いろんなことが試されるような気がします。そのときに、誰が本当に支えてくれるのかが見えるような気がして。だから僕はすごく感情移入するし、ドラマを感じる。そういう世界を描いていたら、応援してくれる視聴者の人がすごく多くて、10年続くような番組に育ちました」
スーパースターの、まさかの転落劇
菊野は少年時代、水島新司の『野球狂の詩』を愛読していた。クビになった投手がバッティングピッチャーから再起を図るストーリーや、選手として大成できなかった高校球児が新聞記者になってグラウンドの物語を追いかける姿に心ひかれ、ページがすり切れるほど読み返した。
東京大学に進学後は巨人の私設応援団「巨真会」に入り、東京ドームで年間80試合を観戦した。席取りのお礼として社会人の先輩から晩ご飯とビールをごちそうしてもらい、ライトスタンドでハッピに身を包んで声をからした。

そんな菊野を特に魅了したのが、原辰徳だった。1982年から10年以上「第48代4番打者」として巨人を牽引した頃はもちろん、特に好きになったのが晩年だ。1993年に導入されたフリーエージェント(FA)制度で翌年に落合博満(現・中日GM)が加入すると、原は4番の座を追われる。打順は7番まで下がり、ベンチに座る日々も少なくなかった。
スーパースターが味わった、まさかの転落劇――。だが、菊野はますます心を奪われていった。
「スタメンから外れると『今、どんな気持ちでベンチにいるんだろう?』と、打っている頃よりも気になって、好きになっちゃって。原さんは屈辱も味わいましたが、現在、名監督と言われているのは、そうやって挫折して、選手の痛みを自ら経験したことも大きいと思います」
ファンの歓声を浴びるような名場面だけでなく、悲哀の陰ににじむ葛藤も、ヒューマンストーリーに深みを与える要素だ。そんなコントラストは、見る者の心に訴えかけるものがある。



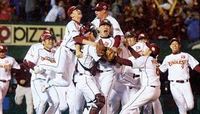



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら