ストーンズの自己改革という意味では、メンバーとレコード会社を変えるという以上に、音楽制作のスタイルを根本的に変えている点が注目されます。
これまでのストーンズは、基本的にバンド・メンバー中心の音創りでした。ゲストの参加は極めて限定的でした。しかし、『レット・イット・ブリード』では、上述のようにソウル歌手やロンドン・バッハ合唱団はじめ多彩な演奏家を積極的に導入しています。興味を引くのは、サキソフォン奏者ボビー・キーズの参加です。サックスの導入で格段に音の厚みが増します。以後、キーズは準メンバーとして長い付き合いになります。
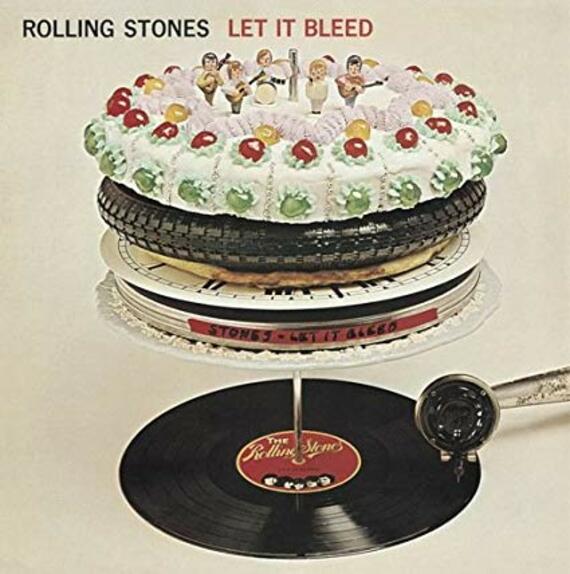
そして、「無情の世界」で、オルガンとフレンチ・ホルンを担当したアル・クーパーにも注目です。この人は、ボブ・ディランの最高傑作「ライク・ア・ローリング・ストーン」でオルガンを弾いていたスタジオ・ミュージシャン。後年ブラッド・スェット・アンド・ティアーズを率いてアート・ロックの流れを引いた音楽家です。こんな猛者を使いこなしているわけです。
要するに、己を知るに至ったという事です。バンドとしての個性、演奏能力、表現したい音楽を冷徹に見据えて、外部の音楽家を自在に使用する術を獲得したのです。ここから、新しいローリング・ストーンズの快進撃が始まります。
過激な時代を象徴している
第3の理由: 時代と共鳴した音盤である
最後に、『レット・イット・ブリード』は、1969年という過激な時代に共鳴した音盤でもあります。発表されたのは12月5日でした。その翌日、ストーンズは全米ツアーの最終公演をカリフォルニア州中央部のオルタモント・スピードウェイで行いました。
実は、この公演は、オルタモント・フリー・コンサートと銘打って、ストーンズ以下、サンタナ、ジェファーソン・エアプレーンなどが出演。聴衆が20万から50万人とも言われていて、運営は混乱を極めました。結果、黒人の観客が暴走族ヘルズ・エンジェルスの警備担当者によって刺殺される事故が起きます。この模様は、映画『ギミー・シェルター』に記録されています。悲劇以外の何物でもありません。が、そんな出来事をも象徴する音盤です。
さあ新年最初の週末です。今も熱く鮮度抜群の『レット・イット・ブリード』で激動の2019年を駆ける力を頂戴しましょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら