さて、ここで少し寄り道して、文化一般に敷衍(ふえん)を試みよう。西洋文化は、サイエンスとアートを、同じ1軸の2極としてとらえることが多い。この理解は、欧米人には自然にみられる。今仮に、このような考え方を、サイエンスとアートの「同軸論」と呼ぶことにしよう。
欧米文化で育っていないと、サイエンスとアートは1軸の両極ではなく、次元の違う2軸ではないか、と戸惑う。だが、見方によれば、同軸論には一理ある。米国では、日本で「教養」に相当する学部を “Faculty of Arts and Sciences” という。アートとサイエンスは、いずれも真理の追求と社会の改善を目指すものであって、ただその方法論が違う、との理解である。一方はデータや論理に頼り、他方は経験と感性に従う。
もちろんこの分類はあいまいさを内包しており、「計算に基づく芸術」はどうする、と問われれば、中間に置くしかない。グラデーションを持った分布と考えたほうがよかろう。
その考えに従って、左にサイエンス、右にアートを取った軸の上に、文明のさまざまな要素を置いてみよう。
大勢の小天才で1人の大天才を代替できるか
純粋数学は左の端にくる。理論物理学はすぐ隣であるが、抽象概念でなく観測事実を基盤にする点で、数学よりは中ほどに近づく。次いで、天文学や地学、化学などが続く。生物学や医学など、観察と実験に立脚する分野は、さらに右側に寄る。社会科学となると、サイエンスの領域の右端で、アート領域との境目に近い。商工の産業は、この軸の中央ややアート寄りに居場所があろう。工芸となれば完全に右側のアートの領域だ。さらに、文芸、美術や音楽などの芸術が軸の右端に収まる。
サイエンスは客観事実に立脚し、先人の知恵に乗って進む。その進歩に個人による変動要素は小さい。数学者の高木貞治は、仮に時代が1人のガウスを得なかったとしても、大勢の小天才が集まって、いつかその到達点を超えて行く、と表現した。
一方、アートは人の感性から生じるので、個人の存在が大きくありようを変える。ミケランジェロやモーツァルト、シェイクスピアがいなければ、人類の文化遺産に重大な欠落を生じたであろう。小天才がいくら集まっても、それを埋められるとは思えない。

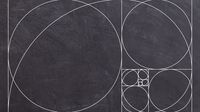





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら