商店街の中の、ばらばらだった店舗同士が、学生を潤滑油のようにして、あるいは血液のようにして緩やかにつながっていく。学生自身はそんなつもりもないだろうし、もしかすると面倒な課題だと思っているかもしれないが、彼らが入り込むことによって、商店街内の関係性が変化していくわけである。
この力は、個店の関係のみならず、行政やNPOや大学まで巻き込んで広がっていく可能性を有している。
あくまで仮説だが、とても興味深い話だ。商店街を活性化するためには、一つには、これまでなされてきたように商店街としての組織をしっかりと構築し、あたかもショッピングセンターのごとく個店を管理統制していくという方法があるだろう。だが、それしか選択肢がないのは少し寂しい。東日本大震災を契機に商店街のコミュニティとしての価値が見直されているように、そこには、もう少し緩やかで持続可能な成長性がうかがえるからである。
学生が入り込むことで、意図せずして商店街にかかわる人々を緩やかにつなぎ合わせ、商店街全体に力を与えていく。その可能性は、統制管理とはまた別の方法なのではないだろうか。柔らかいマネジメント、間接的なマネジメント、そんなネーミングができそうな気がする。
【初出:2013.1.26「週刊東洋経済(65歳定年の衝撃)」】
(担当者通信欄)
小学生の頃、社会科の授業の一環で、校区内にある商店街のお店にインタビューをしに行ったり、一日店員さん体験をさせてもらったことを思い出しました。年齢も年齢なので、お店の方と仲良くなったり、保護者が様子を見に次々来店する以上のことはありませんでしたが、入り込むのが社会人に近い段階にある大学生ともなると、新しいものが生まれてきたり、ビジネスにつながるきっかけが得られる可能性が高まるのももっともなことです。商店街については新雅史さんの『商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道』(光文社)、商店街とセットで語られることの多いショッピングモールについては速水健朗さんの『都市と消費とディズニーの夢 ショッピングモーライゼーションの時代』(角川書店)など、昨年も話題書の刊行が続きました。
さて、水越康介先生の「理論+リアルのマーケティング」連載第4回は2013年2月18日(月)発売の「週刊東洋経済(特集は、投資の新常識)」に掲載です!
【「百貨店」の存在の仕方 その常識が変わるとき】“らしさ”を取り戻すか批判を可能性と捉えるか?そもそも百貨店とは何なのか?
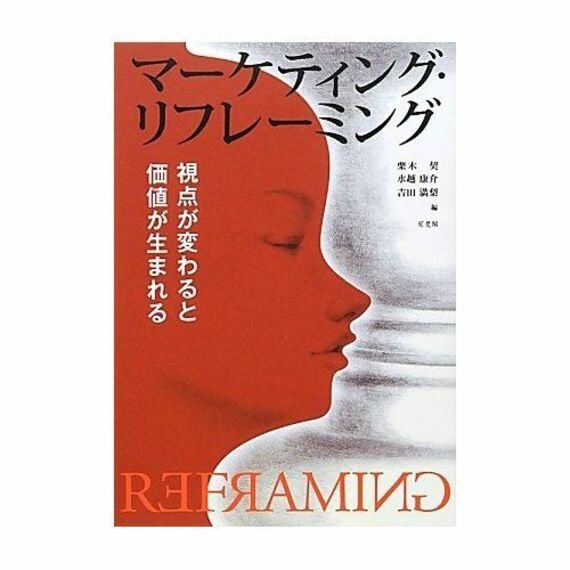
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

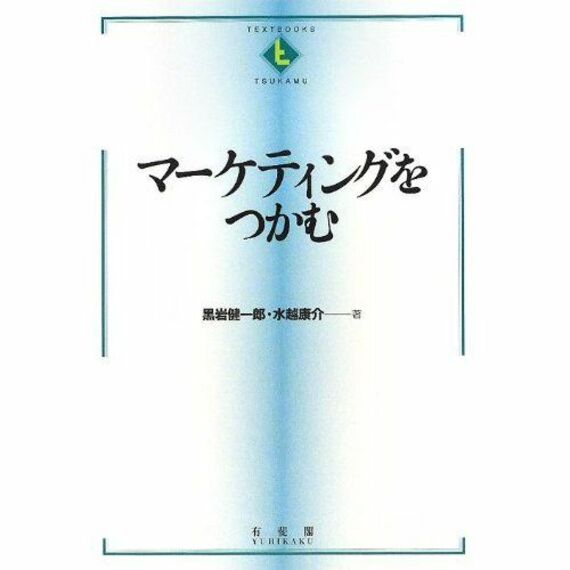































無料会員登録はこちら
ログインはこちら