以前の記事でも書きましたが、難関大学に合格した人の小学校入学前では、「思いっきり遊ぶ」「絵本を読み聞かせ」「好きなことに集中する」ということが共通していると発達心理学の分野でも言われています。やはり、そうなのです。いわゆる伸びる子たちは、勉強をやってばかりの幼少期を過ごしてはいないのです。
それでもやるなら、何に留意すべきか
しかし、そうはいっても「少しは何かを学ばせたい」と思う場合もあることでしょう。そのときに何をすべきでしょうか。
幼児教育が流行しているような状況ですので、さまざまなものを目にする機会があるかと思いますが、個人的には、特殊な勉強は必要ないのではないかと思います。それよりもおすすめしたいのは勉強の基礎・基本、つまり“読み・書き・そろばん”です。
読みは、絵本を使った読み聞かせを、書きは、ひらがな、カタカナや簡単な漢字の練習がいいでしょう。それらを「楽しんでやれるようやり方を工夫する」のです。そして、文字がわかってくると、見るもの聞くものの意味が色々わかってきて、お子さんは知識に対して好奇心を持つようになるでしょう。
“そろばん”は習い事に通うのもいいでしょうが、必ずしもそれでなくても、足し算や引き算といった計算をドリル学習として毎日1枚こなすことを習慣にしていくのでもいいでしょう。
ここで大事なのは、勉強そのものというより、勉強を習慣化させることです。幼少期の勉強の効果は長続きはしないかもしれませんが、日常の中で勉強を習慣化させることができれば、長いスパンでみたときに大きな力となってくるはずです。
全ての未就学児を調査しているわけではないので、私のこれまでの経験と、文献や統計の調査結果の内容からしかお話できませんが、まとめると、次のようなことがいえるでしょう。
以上、ご参考いただき、ご家庭の方針にしたがって、どうすべきかご検討いただければと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

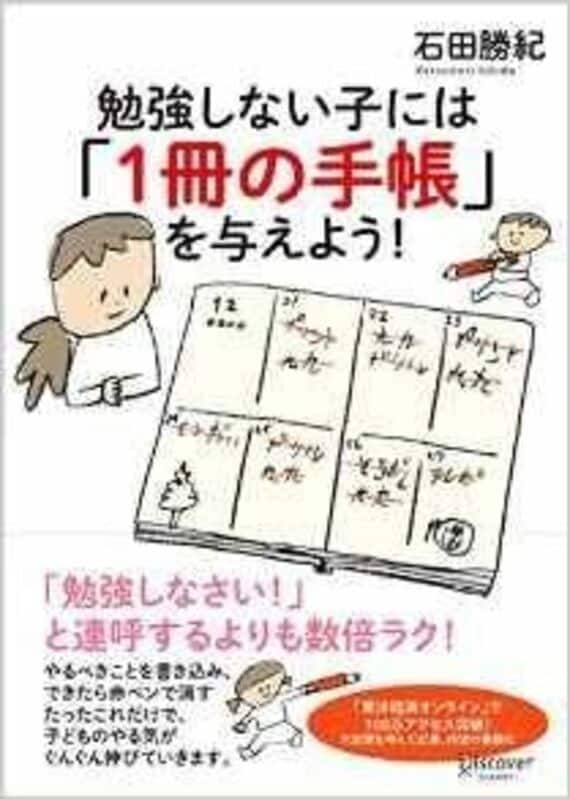






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら