「地方民が憧れたサブカル誌」「ヴィレヴァンでよく見かけた」 "平成"をつぶさに記録してきた、伝説の雑誌『東京グラフィティ』その後の意外な姿
「大のカルチャー好き」と自称する仲野さんは、同誌に掲載されている東京の人々や、さまざまなカルチャーに刺激を受け、芸術系の大学に入学。出会ってから毎号を買い揃えた。
もちろん、就職は同誌の編集部を志望していた。
同誌は社員数名の会社で編集されており、当時正式な形での新卒採用は行っていなかったというが、なんと運よく就職のタイミングで欠員が出て、面接までこぎつけた。そして内定をもらい、卒業後の19年春に上京。編集者として働き始める。
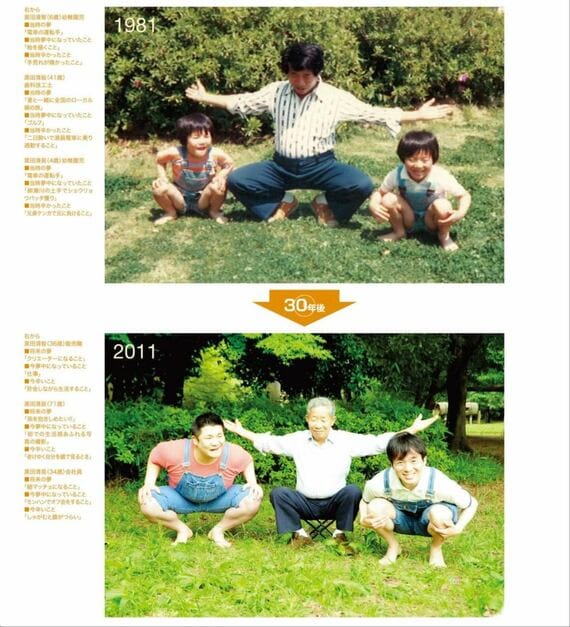
「ヴィレヴァン」とともに時代を歩んできたが…

「もともと就職活動をしておらず、1社しか受けていないのでラッキーでした。ただ、僕が入社した頃には、月刊誌だった『東京グラフィティ』が隔月刊の年6冊に縮小されていて、コロナ後は季刊で年4冊となってしまいました」
熱意あふれて入社したものの、同誌が勢いを失っていく瞬間に立ち会うこととなってしまった。仲野さんは、自身を典型的な読者として位置づけて、衰退の理由をこう分析する。
「雑誌が読者と一緒に年をとっていった感覚はありますね。若者向けのカルチャー誌として出発して当初は中高生がメイン読者だったのに、休刊前は30〜40代の読者がメインでした。
あと実は、熱心な読者は東京だけではなく、僕のように関西だったり、群馬や栃木といった北関東などの、東京に憧れを持っている“上京予備軍”のような人たちもたくさんいました。彼らも憧れの先を、雑誌ではなくSNSの中に見つけるようになったのかもしれません」



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら