どの家臣でも埋められなかった存在…秀長亡きあとに豊臣家がたどった「目も当てられない」迷走ぶり
同年12月には、加藤清正・浅野幸長らの籠もる蔚山城が明の大軍に包囲され、水道および補給路を断たれ、厳寒のなか厳しい戦いを強いられる。加藤・浅野らは翌年正月、西生浦から到着した毛利秀元らの救援隊によって窮地を脱している。
この蔚山城の戦いののち、宇喜多秀家らが戦線の縮小を提案したが、秀吉はこれを却下し、上申者を叱責したという。また、諸将の間でも、加藤清正と小西行長の対立などの内紛が続き、日本軍のなかでも厭戦の気分が強くなっていった。
サン・フェリペ号事件
朝鮮侵略の際、日本軍の間では、戦功の証として朝鮮人の耳や鼻を切り取る「耳切り(鼻切り)」という残虐行為が行われていた。切り取られた耳や鼻は、秀吉から派遣された軍(いくさ)目付けが諸大名から受け取り、塩漬けにして樽に詰め、秀吉のもとに送られていた。
秀吉は慶長2年9月に方広寺の近くに耳塚(鼻塚)を築き、これを供養している。また、同月に、秀吉は、前年に「秀頼」と改名した嫡男の拾を元服させ、従四位下・左近衛権中将に叙任させた(翌年4月に従二位・権中納言に昇進)。
なお、同時期の文禄5年9月には、土佐にスペイン船が漂着するサン・フェリペ号事件が起きている。このとき秀吉は、船荷と船員の所持金のすべてを没収。
この処置に対して抗議した船員が、スペインが宣教活動とともに征服事業を進めていると大言壮語したことや、イエズス会士によるフランシスコ会への讒言もあり、当時、畿内で活動していたフランシスコ会修道士らが捕らえられ、同年12月に26人が処刑されている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

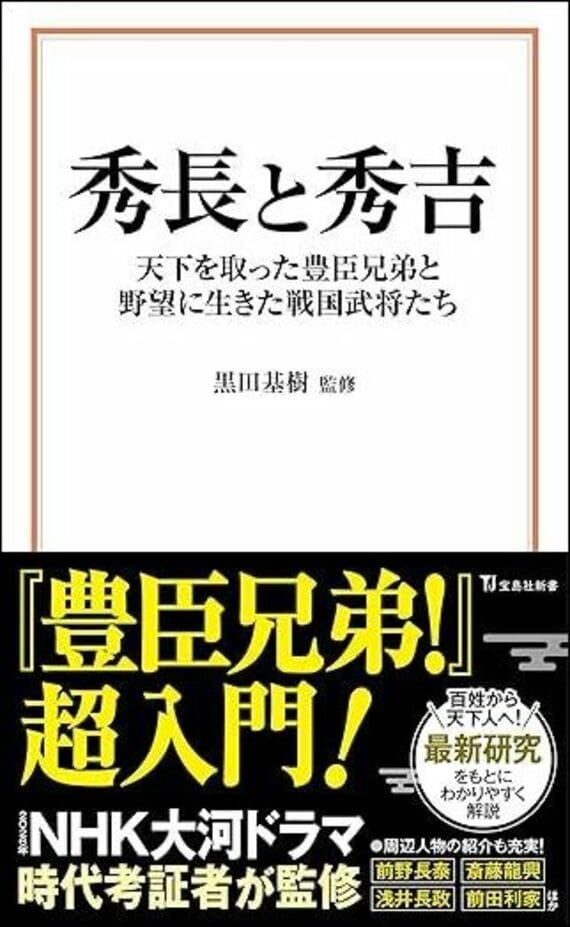































無料会員登録はこちら
ログインはこちら