「求人や契約書の『実働8時間』『休憩60分』『法定休日』といった記載は雇用契約の典型。マニュアルではミーティングへの参加や服装、コーヒーの入れ方などについても言及されており、強い指揮監督や時間的・場所的拘束がうかがえます。日給制はこうした労働力の提供に対する対価であることは明確。『お世話係』や雑用という業務内容や、事実上の24時間拘束という点も労働者性を補強します」

こんな業務委託契約はおかしい
アヤさんは音楽祭での働き方をこう振り返る。
「最初になぜ雇用契約じゃないの?とは思いました。ただ具体的な仕事内容が書かれたマニュアルを渡されたのは勤務初日でした。指揮命令を受ける場面がほとんどで、こんな業務委託契約はおかしいと感じましたが、契約書には損害賠償や契約解除の規定もあり、なかなか言い出せませんでした」
アヤさんが、財団法人に出資する自治体に対して働き方の苦情を申し入れることができたのは、音楽祭も終盤になってからだった。
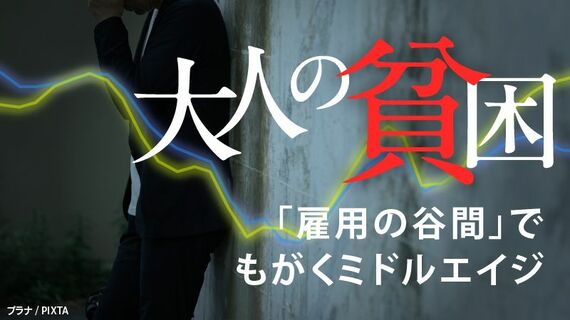
財団法人側はどう思っているのか。取材に対し、担当者は次のように答えた。
「(苦情があったと聞き)社会保険労務士に相談したところ、フリーランスとしての事業者性はあるが、労働者性を持つ部分もあると指摘を受けました。現状のままでよいとは思っておらず、来年度以降、改善が必要な点については見直したいと考えています」
アヤさんはきっとこれからも非正規労働者として働く機会が多いだろう。それゆえに「今回のような契約が問題なしとなれば、民間の幅広い業種でも『雇用契約じゃなく業務委託契約でいいか』という考えがまかり通ることになってしまいます」と懸念する。
自治体や公共性の高い団体の“作法”は民間企業にも波及する。多くの非正規労働者にとって音楽祭の未来は他人事ではない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら