サンマ、カツオ、サバ…要注意!「アニサキス症」の背景と抑えておきたい対処法:激しい腹痛だけじゃない「危険性」とは?《医師が解説》
魚を購入する際はより新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で購入した際は速やかに内臓を取り除くことが重要です。
魚が死んだ後、時間が経つとアニサキスは内臓から筋肉へ移行します。そのため、新鮮な魚であっても、購入したらすぐに内臓を除去し、よく洗浄することが大切です。また、内臓を生で食べないことも基本的な注意事項です。
魚を調理する際は切り身をよく観察し、白い糸状のものがないか確認します。目でみてアニサキスを確認し、除去するのです。アニサキスは肉眼でも確認可能な大きさ(約2~3cm)なので、注意深く見れば発見できます。
多くの人が誤解しているのが、伝統的な調理法による殺菌効果です。
一般的な料理で使う酢や塩で漬けたり、しょうゆやわさびを付けたりしても、アニサキスは死滅しません。寄生虫対策としては不十分であることを理解しておきましょう。
アニサキスに特に注意が必要な人
注意が必要なのは、過去にアニサキス症を経験した人やアレルギー体質の人です。一度アニサキス症を患うと、体内でアニサキスに対する抗体が作られ、次回食べたときに、重篤なアレルギー反応を起こすおそれがあります。
魚介類を頻繁に生食する人、特に漁業関係者や料理人は、知らないうちにアニサキスを口にしている可能性が高いため、アレルギーを持っているかもしれません。気になる場合は、内科などで相談してみてください。
外食時にも注意すべき点があります。
回転寿司チェーンなど大手では、食材の冷凍処理や品質管理が徹底されていることが多く、安全性が高いとされています。一方、個人経営の店舗では、仕入れから調理まで店主の判断に依存する部分が大きいため、信頼できる店舗を選ぶことが基本です。
アニサキス症への対策は、個人や飲食店レベルでの予防意識の向上と、社会全体での取り組みが重要です。消費者への正確な情報提供、食品事業者の安全管理の徹底など、多角的なアプローチが必要です。
研究面では、より簡便で確実なアニサキス検出方法の開発、新しい治療法の探索、アレルギー反応のメカニズム解明などが進められています。また、気候変動による海洋環境の変化とアニサキス分布の関係についても、継続的な調査が行われています。
日本の豊かな魚食文化を維持しながら、安全性を確保するためには、正しい知識の普及と実践が不可欠です。1人ひとりが適切な対策を講じることで、アニサキス症のリスクを最小限に抑え、安心して魚料理を楽しむことができるでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




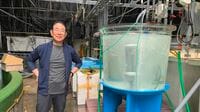


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら