窪田:10代の頃は、スクールカーストが生まれがちです。よく勝ち組、負け組、という言い方をしますが、そんなふうに子どもたちを分けないために配慮された教育のあり方なのですね。
田村:そもそも学力だけでは、この世の中は乗り越えられないですからね。日本の教育ももともとはリーダーを産む全人格教育だったと思うのですが、戦後に優秀な指示待ち人間を産む偏差値教育にシフトしてしまい、学校も学部も偏差値で選び、就職先も就職人気ランキングで選んでしまっているように思います。その結果、就職にも勝ち組、負け組という言葉が使われています。
でも、今はアメリカが特にそうですが、SP500に入っている大企業でも盛者必衰、下剋上の連続でどんどん入れ替わります。勝ち組だと思っていてもどこで転落するかはわからない。偏差値→就職人気ランキングというルートは危険です。
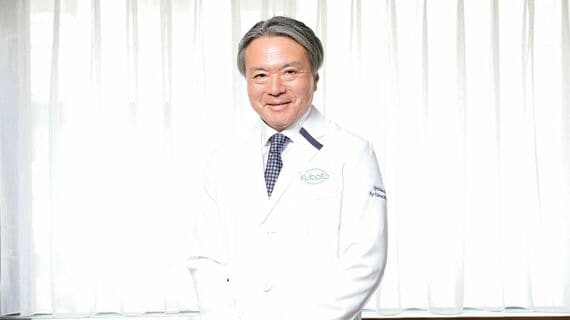
それとインターナショナルバカロレアでは自分がオーナーになる発想ですから、日本のような高年収での雇われを目指すような発想がそもそも薄いです。人生は長くなり、テクノロジーの進化が職の安定を根幹から崩していきます。どんな時代が来ようとも自らの頭で考えて生き抜く力を養うような教育が必要だと思います。
母子留学も活発
窪田:まだ日本の学校ではそうした考えが浸透しているとは言えませんが、すでにそうした意識を持って、アンテナを立てている親御さんたちはいますよね。
田村:そう思います。私が以前、日本で暮らしていた地域のコミュニティには、お子さんを海外のサマースクールに連れ出したり、母子留学をされたりと、積極的に動いている方たちもいます。十数年前と比べると、日本もだいぶ変わってきたと感じます。
窪田:親御さんたちの意識と行動が変わってきているというのは興味深いですね。次回は、田村さんが体験された世界最先端の「長寿クリニック」の話題を中心に、シンガポールの健康事情をお聞きしていきます。
(構成:安藤梢)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら