昭和初期と比べて現代人の「噛む回数」は半分に減少していた…メタボを招く早食いを防ぐための、調理法のちょっとしたコツ
ということは、使う食材は同じでも、硬く、食べにくくなるように調理すれば、ダイエットに役立つことになりますね。
1 食材を大きく切る
煮物でも炒め物でも、食材を大きく切れば、ひと口で飲み込むことはできません。目安は3~4口で食べるくらいの大きさです。通常サイズのジャガイモなら2つ割り、ニンジンなら3つ割り、玉ネギも4つ割りくらい。根もとが多少つながっていてもOKです。
エリンギは丸1本くらいのイメージで。エノキタケや舞茸は、株をざっと分ける程度にしてください。
2 硬さを残す
コリコリ、シャキシャキした食感を残すために、茹でるときも炒めるときも、調理時間は短めに。電子レンジで下ごしらえするなら加熱時間を短くし、海藻、切り干し大根などの乾物は、水で戻す時間を短くします。
以前、料理研究家から、コンニャクは塩もみしてから、しっかり加熱すれば、驚くほどプリプリになると教えていただきました。もちろん、コンニャクも大きく切って、味がしみるように、表面に浅く切れ込みを入れます。
3 できるだけ皮をむかない
野菜の皮をむかずに調理すると、しっかり噛まないと飲み込めません。皮ごと食べられる野菜は、大根、カブ、ニンジン、レンコン、カボチャ、ゴボウ、長芋、ジャガイモ、サツマイモなど、たくさんあります。
農薬が気になるなら無農薬野菜や有機野菜を選んでください。
このなかで、お店で売っているニンジンには、すでに皮がないという話はご存じでしょうか。ニンジンの皮は薄いため、収穫して洗浄する段階でむけてしまいます。だから、わざわざ皮をむこうとする必要はないのです。
ピーマンはワタも種も捨てずに食べる
インターネットなどで調べると、野菜の皮には各種のビタミン、ミネラル、さらには食物繊維が豊富なので、食べなきゃ損! という記事をみかけます。実際のところはどうでしょうか。
たとえば、収穫したばかりの皮つきのニンジンと、皮がむけたニンジンを、同じ100gあたりで比べると、β(ベータ)‐カロテンは6900μg(マイクログラム)と6300μgで、約9%減です。
ただ、食物繊維はどちらも2.8gと、ほとんど変わりません。栄養に関しては、「皮をむかないほうがよい」程度といえます。
皮だけでなく、ピーマンやカボチャは種と、そのまわりのワタと呼ばれる部分も食べられます。わざわざスプーンでくり抜いたりせず、そのまま、大きく切った果肉と一緒に調理しましょう。
ブロッコリーは茎ごと、こちらも房を大きく分けて使います。
野菜は皮にも種にも茎にも独特の風味があり、野菜本来のよい香りがします。ダイエットを目指す人は、こまごまと盛りつけた芸術的な料理ではなく、自然を感じられるダイナミックな料理を作りましょう。
食材の硬さを残して大きく切れば、GI値を下げる効果も得られます。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

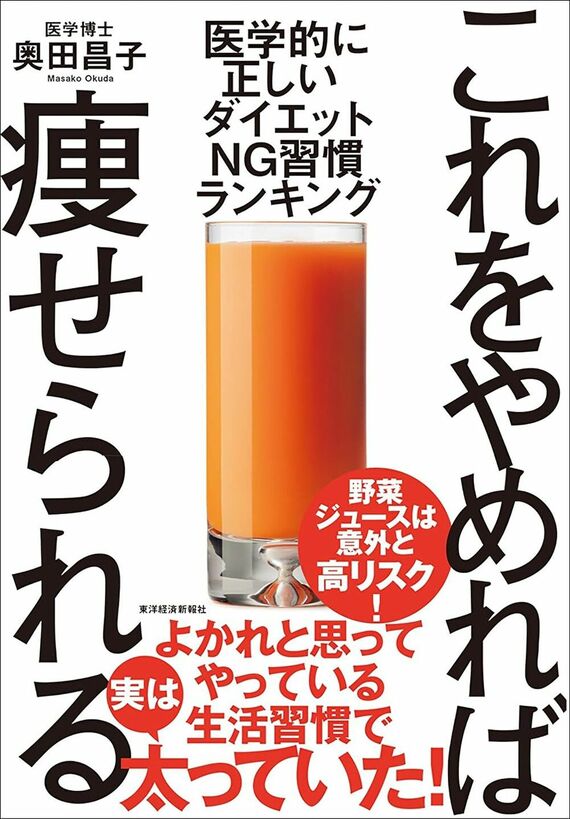






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら