「覚悟はできとるんじゃろうな」ーー野球部顧問からの叱責を苦に16歳が自死 それから13年たった今も苦しむ父親が訴えること
筆者は、岩手県の再発防止対策委員会についても取材したが、毎回遺族と担当弁護士を招き、遺族が選んだ有識者らも含め意見を丁寧に聴き取っていた。そこには遺族に寄り添う姿勢が見られた。
2021年1月、県立高校の空手部員が自死した沖縄県の事件を受け、沖縄県教育委員会は7月に、当該顧問を懲戒免職にした。翌月には第三者委員会設置を決定した。翌年からは、部活動の実態や設計に詳しい専門家や、スポーツ心理学者ら有識者を中心とした沖縄県部活動改革推進委員会を立ち上げ、暴力や暴言、ハラスメントのない部活動を目指して生徒自身が部活動のあるべき姿を協議する高校生検討委員会(県教育庁主管)を複数回開催。話し合いによって集約されたものが「沖縄県高校部活生メッセージ2023~変えよう部活、変えよう未来~」として発表された。
今後は「沖縄県のスポーツを新しい指導スタイルに転換するプロジェクト」として、競技団体ごとに小・中・高の全カテゴリーが協働して指導改革に取り組むやり方を推し進めるという。
いまだ大きな乖離がある、遺族側と県教委との認識
筆者は遺族の対応を担う岡山県教育庁に出向き、有識者の推薦先を遺族に無断で変更したことや遺族の話をきちんと聞いているかといった質問状を持参し取材を申し込んだが「面会での取材対応は控えさせていただき、ご質問については、次のとおり回答いたします」とメールが来た。
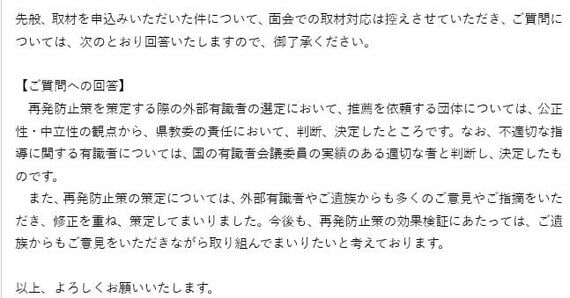
質問に対する明確な答えはなく「再発防止策を策定する際の外部有識者の選定において、推薦を依頼する団体については、公正性・中立性の観点から、県教委の責任において、判断、決定した」「再発防止策の策定については、外部有識者やご遺族からも多くのご意見やご指摘をいただき、修正を重ね、策定した」との返事だった。

不適切指導問題改善の道半ばで亡くなったA君の母親に、筆者は2021年6月にオンラインで取材した。母親は画面の向こうで涙ながらに声を振り絞って訴えた。
「Aは弟とけんかをしたこともなく、兄弟仲が良くて。バカとか死ねとかそんな汚い言葉は使ったことのない子たちでした。だから部活動で先生から怒鳴られたり、死ねとか言われたりしたら、相当ショックを受けたと思います」
「今後(防止策が)適用される道のりを考えると不安です」
遺族側と、県教委との認識にはいまだ大きな乖離があることがうかがえる。こうした痛ましい事件の再発を防ぐには、遺族の思いを受け止める覚悟がもっと必要なのではないかと感じられてならない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

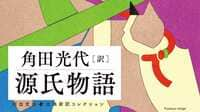


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら