「覚悟はできとるんじゃろうな」ーー野球部顧問からの叱責を苦に16歳が自死 それから13年たった今も苦しむ父親が訴えること
こうしてA君の死から実に13年が経過した。苦しむ遺族にとっては途方もない年月だ。その長さを物語るかのように、遺族に対応する窓口は生徒指導推進室から途中で教育政策課に替わり、人事異動もあって担当者はすでに6人目になる。遺族は彼らとのメールのやり取りを書類化しているが、2021年3月からの4年分だけでも250ページに及ぶ。
「(県側の)担当者は替わりますが、受ける印象は変わりません。(県教委に)一番お願いしたいのは、遺族に寄り添った対応をしてほしいということです」と父親は吐露する。

例えば、子どもの自死に関しての事案を抱える他の都道府県は「第三者再発防止検討・検証委員会」を設置しているところが多い。ところが、A君の父親が同様の組織の設置を岡山県に要望したところ、それは却下された。その後、第三者による対策組織は設置されぬまま、県教委の中で再発防止策を作成することになった。
自死の原因を探る際に第三者委員会は置かれたが、再発防止策を作成する段階においてはそれはなされなかったということだ。
県教委が主導する組織に外部有識者は招かれたものの、そのメンバーの選定プロセスについても父親は違和感を抱いている。
誰がメンバーに入るかによって報告書の内容は大きく変わる。そのため父親は、不適切指導に関する専門家など外部有識者を含む6人の加入を求めた。しかし、その半数は受け入れられなかった。不適切指導に詳しいとされる有識者も、遺族には相談されることなく変更されていた。
自死に至る原因を調べるための第三者委員会が残した調査報告書には、「遺族の話をきちんと聞いて再発防止策を策定する」旨が明記されている。だが、こうしたことを見ると、それが尊重されているようには見えない。
「(県教委との対話には)心底疲れました。でも、やり続けなくては息子に申し訳ない」と父親は声を絞り出す。ここまで心血を注ぐのは、息子への贖罪の気持ちからだ。
自身の存在価値を否定された息子の絶望
A君が受けていた暴力は次のようなものだった。すべて県の調査で認定されているものだ。
A君は、野球部の顧問による「死ね」「帰れ」などの暴言や、感情的になるとパイプいすを振り上げる暴力行為に苦しんでいた。高校1年の2学期、野球部日誌に「自分は無意味な存在だった。自分はチームにとって存在価値がないので、これからはチームの役に立つよう頑張りたい」と書いている。
ところが、3学期にあたる2012年2月、野球部日誌に「もう自分の存在価値も目標もわからなくなった」と記述。2年生になった5月の鳥取県での遠征試合では、顧問から捕球できないところにばかりノックされ「声を出せ」と怒鳴られた。さらに「いらんわ。おまえなんか制服に着替えて帰れ」と叱責され、その日以降も「Aはルールを知らんから、誰かルールを教えちゃれ」などと罵倒が続いた。

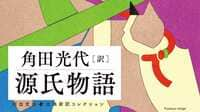


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら