大阪・関西万博に台湾が「一民間企業」として参加せざるをえない理由、中国大陸との関係に左右されてきた歴史
そして、今回の大阪・関西万博では、民間企業「玉山デジタルテック」名義での参加が確定した。これに対して、国民党側から「台湾館」として参加することができた上海万博と対比したうえで「国家の格を辱めるもの」などと批判する声が上がった。国民党も民進党も、台湾の各政党の反応は、ある種の定見のなさを示しており、その時々の立ち位置によって変わっている。
台湾と中国大陸とのその時々の関係によって、万博での扱い、参加名称は変化する。中国大陸は、「1つの中国」の原則を堅持して台湾との統一を目指しており、その立場は終始一貫して揺らがない。良し悪しとは別として、これは事実だ。その中国大陸の立場を尊重して良好な関係を維持できれば、台湾が希望する「台湾」名称を使用することができる。
「92コンセンサス」という存在
国民党がこれまで台湾の独自性を維持しながら中国大陸との良好な関係を構築できたのには、「92年コンセンサス(九二共識)」というキーワードがある。1992年に台湾と中国大陸の窓口団体が香港で開催した会議で「1つの中国」について合意したとして、これを「92年コンセンサス」と呼んでいる。
台湾の中華民国憲法は、実は共産党との内戦に敗れて台湾に撤退する前、中国大陸にあった時代の中華民国を踏襲して「1つの中国」に基づいている。台湾として中華民国を追い出した中華人民共和国が主張する「1つの中国」は認められないが、「1つの中国」という抽象的な概念の上では中華民国も共通している。
つまり台湾側は中華民国として、中国大陸側は中華人民共和国としての「1つの中国」であっても、互いにそれは問わない。国民党は、この「1つの中国、各自解釈(一中各表)」という概念によって台湾の人々を説得した。「1つの中国」であっても、台湾が中国大陸に併呑されることを意味するわけではないというわけだ。
「92年コンセンサス」というそのままでは意味のわからない用語は、中国人同士ならではの一種の言葉遊びの極みだ。物事に白黒を付けないことで双方の面目を保ち、曖昧さを残して双方の対立点を際立たせないという手法だ。







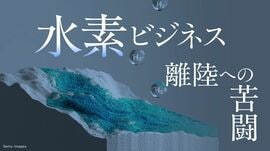





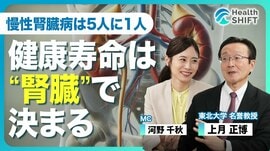

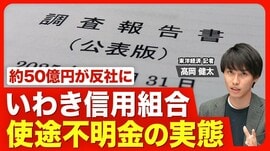
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら