大阪・関西万博に台湾が「一民間企業」として参加せざるをえない理由、中国大陸との関係に左右されてきた歴史
中国大陸側は、「92年コンセンサス」が「1つの中国、各自解釈」だという国民党の主張には同意していないものの、これが「1つの中国」を確認したものとして双方の交流の基礎だと位置づけている。そして、台湾が「中華民国」を称することについては認めはしないが、否定もしていない。
しかし、この国民党・馬英九政権の中国大陸との接近政策は、台湾で次第に大きな反発を引き起こすことになる。その潮流に乗る形で2016年に国民党からの政権交代を果たした民進党の蔡英文政権は、台湾の主体性を守ることを自らの使命とし、「92年コンセンサス」を認めよという中国大陸側の再三の要求を拒否した。
関係悪化という悪循環が始まる
中国大陸側はこれを台湾独立の分裂行為と認定して民進党との交流を断ち、台湾に各種の圧力をかけてきた。それに対して蔡英文政権は、中国大陸に対する批判を繰り返す。関係悪化の悪循環がやまない状況に陥った。
2024年に蔡英文総統を引き継いだ頼清徳総統は、さらに中国大陸との対決姿勢を強めている。このように台湾の主体性を追求して中国大陸との関係を悪化させれば、万博でも「台湾」名称は使えない。台湾としてのプライドを守ろうとして、逆にプライドを傷つけられている。
実を取るか名を取るか。台湾をめぐって矛盾するこの2つの選択肢の間で、民進党政権は後者を選択した。そして台湾は今、国際的な活動空間を狭め、平和を脅かされ、苦悩している。
日台関係は友好的とされ、日本人も台湾の人たちも、多くがそう認識している。「台湾有事は日本有事」という言葉が飛び交い、日台は安全保障で強い結び付きを持つかのような印象を持たれている。
しかし、今回の大阪・関西万博での「台湾館」に関する日本の態度は、台湾の人々に日台友好には限界があることを思い知らせることになった。日台の友好は本物なのだろうか。
ただ、その責任を日本に押し付けられても困る。根本的な原因は、台湾と中国大陸の間の関係にある。
日本と中国大陸の間で国交正常化の際に交わした約束に変更がないという大前提の下で、日本が台湾とどのような関係を構築できるのかは、中国大陸との関係における台湾の知恵と選択にかかっている。大阪・関西万博はそのことを改めて浮き彫りにしたようだ。
(執筆協力:本田善彦)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら







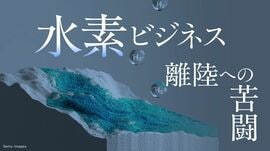





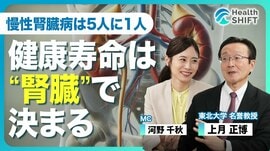

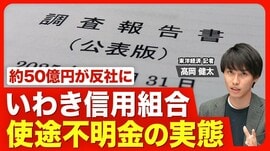
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら