
2012年創業のリープマインドは、業態展開を続けながら先端開発に取り組み、エヌビディアに真っ向勝負を挑んだ (撮影:梅谷秀司)
エヌビディアとの真っ向勝負に挑んだリープマインドの松田総一元CEO(以下、敬称略)には、勝算があった。
「エヌビディアがアピールするGPUのスペックは、それを動かすソフトを最適化した状態での“ピーク性能”。実際にはほとんどのケースで、その数割のパワーしか引き出せていない」(松田)
確かに松田が指摘したとおり「エヌビディアのGPUは、AIモデルの学習において効率的な作りになっていない」ということは、すでに業界では暗黙の了解になっている。だからこそGAFAMは、自社で運用するデータセンター向けに専用の半導体をこぞって開発しているのだ。
リープマインドも「われわれはソフトウェアの会社。ソフトを作りやすい半導体を1〜2年以内にリリースできれば、まだ間に合うはず」(松田)と狙いを定めた。
データセンター向けの学習用チップに参入する時点で、松田は自ら立ち上げた会社を解散する「撤退ライン」を決めていた。従業員や債権者への支払いや、チップ製造のため委託先(ファウンドリー)に発注を出さなくてはいけないタイミングを考えれば、残された時間は長くはない。
出資者や当時60人ほどいた従業員にも「撤退ライン」を伝えていた。
ファウンドリー3社との交渉
だが、そもそもチップを製造するために、いくら必要なのかがわからなければ、資金調達の交渉もできない。仮に調達できても、ファウンドリーへの発注枠を確保しておかなければビジネスができない。
松田はファウンドリー事業を手がけているアメリカのインテル、台湾のTSMC、韓国サムスン電子との直接交渉に乗り出した。
2024年1月。松田はインテルのパット・ゲルシンガーCEO(当時)との直接交渉に挑んだ。

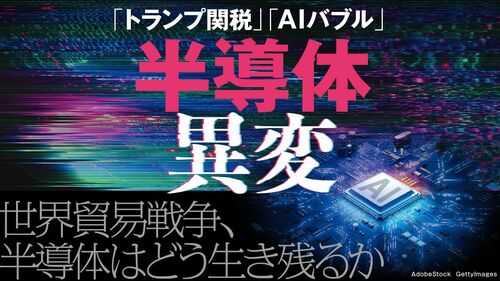































無料会員登録はこちら
ログインはこちら