


大阪万博が残した遺産
このほか、大阪万博で採用されてその後日本国内に普及したものとしては“動く歩道”や“ガードマン”などが挙げられる。動く歩道は、現在は空港、駅構内、大型施設へのアプローチなどに広く用いられているが、最初に導入されたのは1967年の阪急梅田駅。1970年の万博会場で用いられたことで、その後の各地での導入につながった。
また、入場者数の多さが予測された万博では、会場内の警備と案内に民間の力を頼るしかないと、民間警備会社計8社と契約。会場周辺の交通整理と治安確保、VIPの警護は警察が担当し、それ以外の来場者案内、混雑対応や会場警備は民間の警備会社が担当した。
その任務担当ぶりが注目され、万博後も警備会社への依頼が舞い込むようになったそうだ。
万博は、1970年9月13日の会期終了後、千里会場のほとんどのパビリオンは解体。現在、万博記念公園内に残されている当時の建物は、太陽の塔のほか、戦後モダニズムの巨匠である前川國男が設計した鉄鋼館。万博開催時に各国の元首や賓客を迎えた迎賓館。日本民芸館。“夢の池”内の噴水やオブジェ、エキスポタワー解体後の部分などだ。
2018年からは、耐震補強された太陽の塔の館内公開がスタート。塔内部を貫く“生命の樹”や“こころ”“ひと”“いのち”などをテーマに岡本太郎が実現した展示空間や、そのために岡本が描いたスケッチなどが展示されている。
70年万博は、多くの来場者を迎え、数々の大会後の成果をもたらしたと言えそうだ。それは1970年という時代の勢いということもできるが、その55年後の大阪・関西万博はどんな果実をもたらしてくれるのだろうか。
今回の大阪・関西万博では、なんと、アメリカ館で再び“月の石”を、大阪ヘルスケアパビリオンでは人間洗濯機の21世紀版とも言える“ミライ人間洗濯機”が出展展示されるそうだ。
例えば、今からさらに55年後の未来には、どんな遺産が残っているのだろうか。それを知ることができるのは、今回の万博を見にいった現在20代以下の若者ということになりそうだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

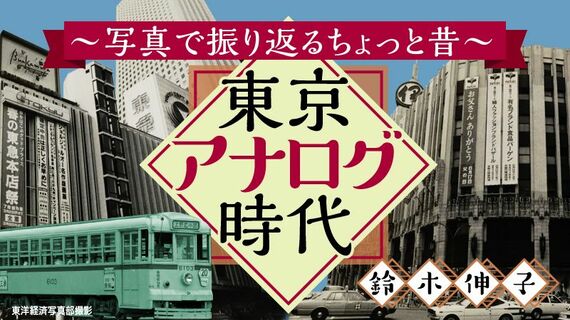






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら