選挙戦で物価高対策として繰り返されるばらまき論争。「ガバメント・データ・ハブ」の導入が解決策となる。

ガバメント・データ・ハブとは、「国民の所得・資産や世帯構成、税・社会保障の負担と社会保障給付などの情報を一元的にまとめ、税・社会保障を担当する行政部門が、必要に応じて相互利用する仕組み、すなわち行政情報の相互利用基盤」のことである。東京財団・森信茂樹氏が提唱したもので、令和臨調(令和国民会議)が提言したばかりである。
本稿執筆時点は、参議院選挙の真っ最中。選挙結果についての予想も花盛りで、自民・公明の与党が過半数を取れない可能性が大きいと報道されているところだ。結果いかんでは、衆参ともに少数与党となり、その場合、政策がことごとく決まらない憂き目に遭う。トランプ関税への対抗措置に手抜かりが生じ、不平等な条件で妥結してしまうと、深刻な景気悪化に陥りかねない。政治の脆弱さが露呈すれば最後のツケは国民が払うことになる。
そうでなくとも関税の行方を見守る間は、様子見を決め込む企業や個人が多い日本ではいよいよお金が動かなくなってしまう。せっかく上昇機運が見え始めた景況感に水を差すだけでなく、5%程度の賃金上昇を3年連続させてきた実績が元の木阿弥となりかねない。
将来世代への配慮が必要
今はそうしたリスク選択をしてしまうかもしれない状況下にある。選挙の争点は、周知のとおり物価高対策だ。しかも物価高をどう抑制するか、物価高に負けない賃金上昇実現にはどうするのが有効かといった議論ではなく、物価上昇での生活苦をどう和らげるかが焦点となっている。これでは消費税減税と給付金支払いを二項対立として捉えるだけだ。目先の手取りのみを意識する状態で、将来世代への配慮はいっさい感じられない。
消費税減税は一律の給付金対比で、いくつかの点で見劣りする。第1に、財源が希薄だ。第2に、減税にはシステム対応も含まれ、時間とコストが膨大となる。実際の適用は数年後となり物価高は収まっているかもしれない。つまり時期がずれてしまいかねず、即効性に疑念が残る。第3に、期限を設けた消費税減税は、おそらくその期限を守れず、ずるずると延長となりかねない。

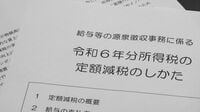









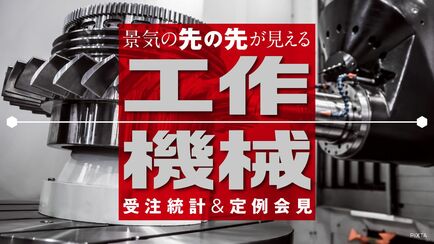






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら