
一度死んだら、二度死なぬ
「一度死んだら、二度死なぬ」とは、江戸中期の禅僧、白隠禅師の言葉です。
日本で禅が生まれたのは、親兄弟が殺し合うような時代、死が身近にあった鎌倉時代のことです。死の気配を濃厚に感じながら、人はどう生きればいいのか。特に武士は、自分の生きる拠り所を模索しました。
禅は、そのとき「今、この瞬間」をひたすらに生きることを説きました。白隠禅師の「一度死んだら、二度死なぬ」という言葉が意味するのも同じことでしょう。人は一度しか死なないのだから、その死を迎えるまでの間を必死に生きるしかない。だから「生き切れ」。白隠さんはそう言っているのだと思います。
それは戦国の世に限ったことではありません。
生きているうちは生き切ること以外に人間にできることなどないのです。過ぎてしまった後悔も、まだ起こってもいない未来についての不安も、考えたって仕方ない。そんなことをすれば、不安が不安を呼び、心を蝕んでいくでしょう。
ひとつ息をするこの瞬間にも、全力を注ぐことです。そうすれば、余計な思いに囚われることはありません。たとえ死が目の前に迫っていても、です。

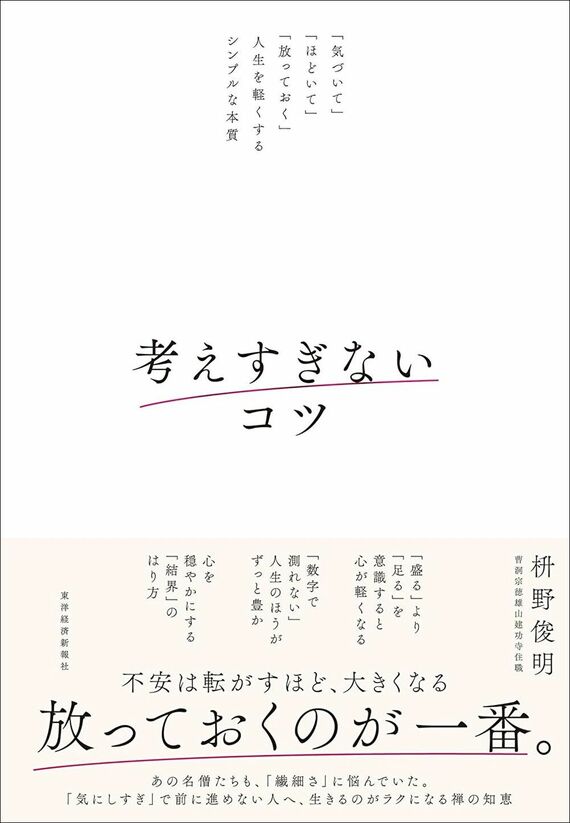






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら