現役の若手が語る「職業としての研究者」のリアル 論文は質より量?「永年雇用」までの長い道のり
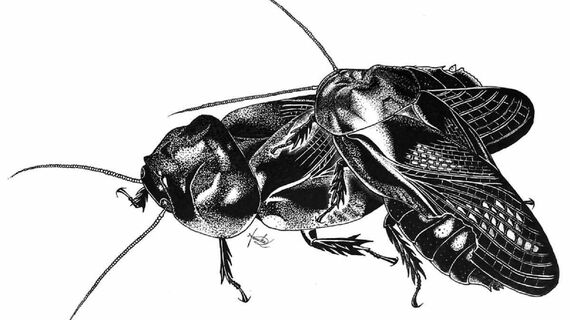
研究者はどうやって生きているのか
研究職はどういうことをしてお金をもらっているのか、不思議な職業の一つかもしれない。どのようにして「研究者」になるのか、日々どのように生きているのかについても、知る機会はほぼないと思う。
おそらくそれは、研究者のキャリアの多様さに一因がある。
研究職に就くルートとして、最もストレートなルートは、大学から大学院に進み、博士課程を卒業して博士号を取得した後、数年のポスドク期間を経て論文をたくさん書いて業績を積む。大学の教員公募に応募し、まずは助教、運がよければ講師に採用されるというものである。
近年は、そのまま永年雇用されるのではなく、5年や7年といった任期がある場合が多い。任期途中で雇用審査が行われるので、これをクリアすれば准教授や教授に昇格したり、あるいは昇格はしないが永年雇用(つまり定年まで)の資格を得るなどして、多くは65歳で退職を迎える(国公立の場合)。
このように途中で審査があって永年雇用に切り替わる制度をテニュアトラックという。聞いたことがある人もいるのではないだろうか。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら