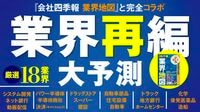BOPビジネスの正しい進め方《第4回・最終回》--現地社会の「起業家」を発掘・支援することが重要
2010年11月に発行された社会的責任のガイドラインISO26000では、企業などの組織がコミュニティの発展に寄与することの重要性が書かれている。この中にはコミュニティで富を創出する方法の1つとして、「起業家を支援すること」も盛り込まれている。
BOPビジネスではこの考え方が重要だ。中には企業が雇い主となり「従業員」としてBOP層を活用するケースもあるが、リスクを取って自分の判断で事業を推進できる「起業家」を育成するほうが成功例は多い。
私たち日本人のように先進国に住んでいると「最貧困層であるBOP層の人たちは意識や能力が低い」という誤解があるかもしれない。
だが、現地には当事者だからこそのモチベーションの高さと事情をよく知るからこその判断力を持つ人材が存在している。この高いマインドセットを持つBOP層をいかに見つけて巻き込んでいくかが成功のカギとなる。
まず、フランチャイズ型のビジネスモデルで、「安全な水の供給」というインフラ事業に成功しているプロジェクトである「ウォーター・ホープ」をご紹介する。これは多国籍企業のペプシコと非営利の教会系財団WTRCが共同出資し、06年からフィリピン・マニラのスラム地区で地元NGOと協力して安全な飲み水の供給を進めているものだ。
マニラでは人口の83%が水道を使える状況にあると言われている。だが、穴だらけの上水道の上を、穴だらけの下水道が通るという貧弱な水道インフラのため、不衛生な水となっている場所が多数ある。安全な飲み水が出る水道だけを考えると普及率はせいぜい40%程度にまで落ち込む地区もあるという。