改革の本質は「経費削減と放任」。

竹内洋氏はこれまでの大学改革の問題点を指摘している。実際この30年間にどんな改革が行われてきたのか。国立大学を中心に振り返りたい。
現在まで続く大学改革の出発点は1991年の大学設置基準の大綱化だ。これにより、画一的だった教育カリキュラムが柔軟化され、各大学が自主的に改革に取り組みやすくなった。それとともに、大学の自律的な変革を求める政策がじわじわと増加していく。
科学技術政策に詳しい広島大学の小林信一副学長は「2000年以降の改革の本質は経費削減と放任だ」と言う。
負のスパイラル
04年の国立大学法人化では運営上の制約を解消し、各大学が自由に改革を進められるようにするとうたわれた。
一方で、人件費など経営の基盤的な経費を賄う補助金である運営費交付金は年1%ずつ減少、その代わりに科学研究費補助金といった競争的資金が増やされる。大学を拡充させるために、競争的資金や寄付金など外部資金を獲得せざるをえない。結果、大学は資金獲得に伴う膨大な事務作業に追われ、教育研究の強化という本来の目標を達成できない負のスパイラルに陥っていく。





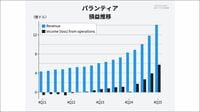



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら