
大手電力会社の「もうけの仕組み」は複雑でわかりにくい。
売り上げはそのほとんどを企業や家庭からの電気料金収入が占めており、比較的シンプルだ。
他方、費用には社員の人件費や協力会社への委託費、発電に伴う燃料費、発電所や送電線など設備投資関連の減価償却費のほか、原子力発電所事故に伴う損害賠償や廃炉費用といった特殊な費用も含まれている。
福島第一原発事故は東京電力ホールディングスによって引き起こされたものだが、原発を保有するほかの電力会社もその一部を「一般負担金」という名称で国に支払っており、その大部分が電力ユーザーに転嫁されている。のみならず原発を持たない新電力会社の顧客も負担を背負わされている。
電力業界ではかかった費用を電気料金の形で回収するのが基本だ。ただ、火力発電用の燃料の価格変動に伴う「タイムラグ損益」など業界特有の一過性の要因もあり、「もうける力」の程度は、単年度では判別しにくいのが実情だ。
一過性の損失が大きい
最終損益を基に検証してみよう。2023年3月期は大手10社合計で1兆円近い赤字になる見通しだ。ただ、この赤字には一過性の要因も含まれており、注意が必要だ。
赤字総額が大きく、経営が厳しいことは確かだ。2022年3月期の赤字額は、全国の原発が全基停止に追い込まれた2013年3月期に次ぎ、過去3番目の巨額になる。
多くの電力会社は「このまま赤字を放置すれば、電力の安定供給に支障を来す」と、危機感を強めている。


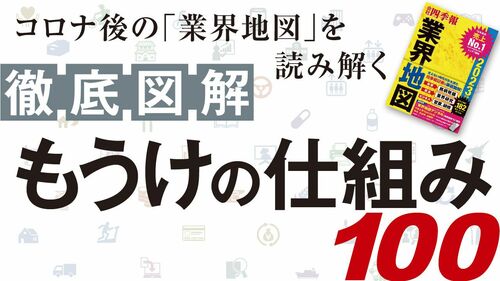
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら