「人間一人では生きていけない」を正面から考える 「個人の原理」と「共同体の原理」の決定的違い
個人と共同体を行ったり来たりするとは、等価交換と贈与を行ったり来たりすることでもあります。そしてそれは、等価交換によってその都度関係をリセットすることと、関係を作っていくことを行ったり来たりすることでもあります。
山村に住みながら個人として生きてもいいし、反対に都市に住みながら共同体の一員としても生きていくことができる。これが、僕が目指している風通しのいい社会です。
「個人」と「共同体」の好循環を目指す
重要なのは、できるだけ多くの人が「行ったり来たり」できる状態にあることです。
そのためには、インターネットを活用することは不可欠になります。インターネットを使いつつ、自律・分散・協調的な社会を目指す。
しかし、それは決してリバタリアンが志向しがちな、社会的強者だけのユートピアを意味しません。その点で、以下の渡辺の報告にはとてもシンパシーを感じています。
スタンフォード大学のビジネススクールは、2017年春に全米600人以上のIT系起業家を対象に政治意識調査を行った。回答者の平均像は、従業員を100人抱え、ベンチャーキャピタルによる投資収益が100万ドル以上あり、年収も100万ドル以上とのこと。
個人個人が尊厳を保ちつつ、できるだけ快適に生きることのできる風通しのいい社会をつくっていくためには、自分だけのことを考えていてはいけないのだと、最近やっと気が付きました。
そういう意味で、IT起業家たちが「再分配」に関心を示しているのは、とても共感するところでもあります。問題はそれをどのように行うのか。そして、その「再分配」とは何を意味するのか。ルチャ・リブロ活動はその実践事例の一つになっていきたいと思っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

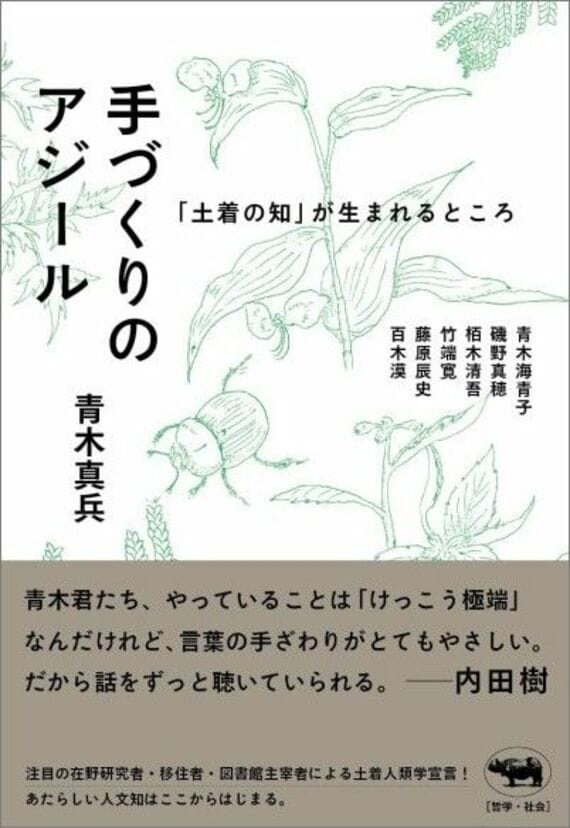































無料会員登録はこちら
ログインはこちら