では、どうすればよいでしょうか。「世界ジェンダーギャップ指数」では、日本は世界146カ国中116位(2021年)と先進国では突出した低さですが、この「ジェンダーギャップ指数」は、各国の移民政策の国際比較指標である「移民統合政策指数」と強い正の相関があります(2020年:日本は56カ国中35位)。
この相関等も考慮すると、「女性活躍」の問題は、出産・育児休暇などの「制度」や「女性の意識」の問題という視野の狭い見方ではなく、「社会の寛容度」の問題と捉えるべきと考えます。
今の日本では「制度を整えたのに、女性活躍が進まないのは女性の問題」という声も出てきそうですが、こうした見方は何の解決にもなりません。女性に責を負わせるのではなく、社会全体として「寛容度」を高めていくにはどうすればよいかを真剣に考え、対策をとっていく必要があります。
女性活躍が進んでいるように見えるアメリカでも、その歩みは決して楽なものではありませんでした。2020年に亡くなられましたが、若い弁護士時代から女性の権利獲得や地位向上に尽力した元・連邦最高裁判事のルース・ベーダー・ギンズバーグ(RBG)の生涯を振り返るとそのことがよくわかります。
その過程で獲得したものも、必ずしも確固としたものにはなっていません。昨年6月、アメリカ連邦最高裁判所が、女性の妊娠人工中絶権を認めた1973年の判決を破棄したことは、その象徴的な事例です。日本でも「選択的夫婦別姓制度」が1990年代半ばから議論されていますが、まだ立法化に至っていません。
既得権益からの反発は世界共通
冒頭で触れたニュージーランドのアーダーン前首相も在職中、「若い女性リーダーに対する誹謗中傷」に悩まされたといわれています。女性活躍は社会課題とされながらも、つねに「既得権益を脅かす力」とみなされ、強い反発が伴うことは世界共通です。近年、さまざまな「分断」が強まり、世界全体の寛容度が低下していることも大きな逆風です。
しかし、閉塞感が強まり先行き不透明な世の中で、国や企業が、レジリエンスを高め、成長を続けるには、女性を含めた「多様性」がカギであることはいうまでもありません。
日本でも、「真の女性活躍社会」の実現までの道のりは極めて厳しいですが、まずはこの問題が制度や女性の問題ではなく、「社会構造・意識に起因する寛容度」の問題であり、その寛容度を高める努力が日本経済再活性化のカギであることを社会全体で再認識することが重要です。
そのうえで、その土台となる改革を一つ一つ、着実に積み上げていくことが、次世代に対する私たちの責務であると思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


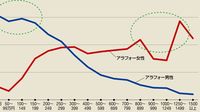






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら