コロナ禍やウクライナ先頭が引き起こした世界的不安を解消できるのか。「2023年大予測」特集の政治・経済パートから抜粋。

輸出回復の遅れも収支悪化に拍車

財務省が2022年12月に発表した10月の国際収支統計(速報)は、9カ月ぶりの経常収支赤字だった。主因は1兆8754億円に上る貿易赤字だ。原油価格の高止まりや石炭価格の高騰、円安によって、エネルギー関連の輸入額が膨らんだ。
22年はまさに貿易赤字の拡大が国際収支での焦点だった。世界的な脱炭素化の流れや、ウクライナ戦争による脱ロシアで、原油や天然ガスなどエネルギー価格は上昇。化石燃料に依存する日本にそれが直撃した。さらに貿易赤字による実需の円売りもあり、円安が加速し、輸入額が膨張した。
輸出回復の遅れも収支悪化に拍車をかけた。中国のゼロコロナ政策によって、現地で新型コロナ感染が再び広がり出した22年3〜5月には、上海など主要都市がロックダウンに追い込まれた。工場の稼働停止や港湾の稼働率低下などで物流網は混乱。日本でも自動車業界を中心に部材不足に陥った。そのため年後半に入るまで自動車を中心に日本の輸出回復は遅れた。

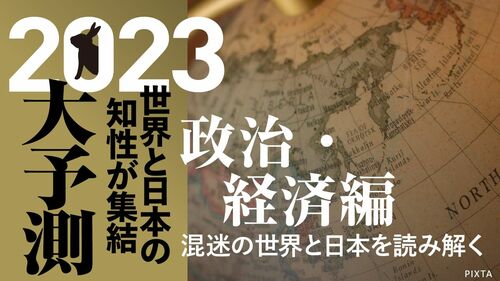



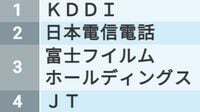



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら