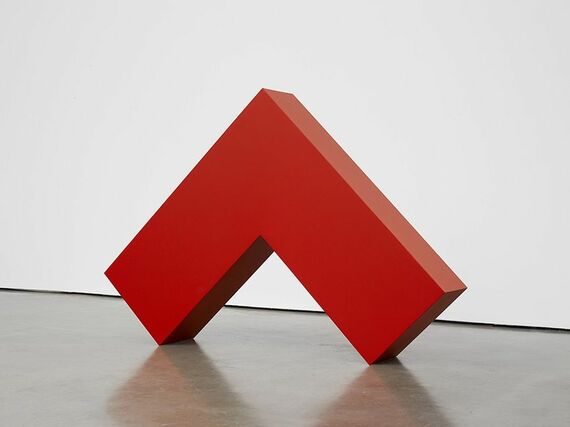
須賀:日本のアート界のパンデミックに対する反応はいかがでしたか?
片岡:日本の美術館の大半は国公立の美術館で、予算消化型ですから、演劇、音楽、映画業界のような興行型のビジネスモデルとは異なり、補償を求めるロビー活動もほとんど見られませんでした。アーティストや美術関係者への補償も文化庁は補正予算を組みましたが申請状況は鈍かったと聞いています。
須賀:そうなんですね。
片岡:パンデミックと直接は関係していませんが、今日ほど複雑な世界のなかで日本の美術館が存在感を保つには、グローバルなネットワークを持つことは極めて有益です。国公立の美術館の研究員や学芸員の方は、原則兼業が難しく、国際展のキュレーターを務めるために美術館を辞職された例もあります。
私は森美術館の柔軟な制度のおかげで、海外で仕事をしたり、組織の外でいろいろなプロジェクトに携わってきたりしたことで、大変多くを学び、世界各地に信頼できる友人もできました。組織の外に出て、自分や日本の立ち位置を客観することは、最終的には所属している組織のためにもなり、より広く言えば、日本のためにもなると思います。今後、兼業が許されていく中で、国公立の美術館でも、そのようなことができるようになればと感じています。
日本のアート界の現状
須賀:グローバルにおける、日本の現代アートの立ち位置については、どのようにご覧になられていますか?
片岡:ダイバーシティーとサステイナビリティーへの取り組みは、アート界でも不可避の課題になっていますが、日本の文化的多様性は、かなり遅れていると言わざるをえません。ニューヨーク、ロンドン、パリといった大都市と比較しても、東京はいちばん文化的多様性が低い。
人種的なバランスを見ても、東京都の外国人率は10%にも満たない。ロンドンであれば、人口の約4割が人種的マイノリティーですし、ニューヨークも白人人口は全体の4割くらいですから、人種、宗教、言語の多様性が高く、まさに、人種の“るつぼ”です。さらに言えば、世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数によれば、日本は153カ国中121位というお粗末な状態。そういった意味でも、日本の文化的多様化への意識改革は急務です。それはおのずと現代アートの評価にも投影されていると言えるでしょう。
企業も多様化という課題に取り組む必要性はわかっていても、何をどうしたらいいのかわからないような状態にあるんだと思います。今は、とりあえず、女性の社会進出を持ち上げているのだと思いますが、より多種多様なダイバーシティーへの取り組みが必要です。女性館長が注目されること自体が、多様性に乏しい日本の状況を表しています。
須賀:目の前の社会が多様性に欠けているからこそ、日本人は多様性の問題を正しく理解するために努力し続ける必要がありますよね。例えば、BLMの運動に対しても、彼らがなぜ、そんなに怒っているかということを、必死に理解しようとして初めて、グローバルで日々起きているダイバーシティーの問題について想像することができるようになると思います。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら