──コロナによる在宅勤務で時間管理の難しさを痛感した今、日本人も考え直す好機かもしれません。
在宅での効率の上げ方に、悩んだ方も多いんじゃないでしょうか。振り返って「あの会議は本当に必要?」「あの作業に時間をかけすぎでは?」とか、従来の当たり前を疑うきっかけになったかもしれない。まずは個人から、できることはたくさんあると思います。
今回、編集の方と話したのが、制度の話にしてしまうと読者は「ああ、ハイハイ」になりがちだから、もっと個に落とした話にしよう、ってことでした。コロナがもたらした機会を、次に生かさなきゃいけないと思います。
フィンランドだって完璧ではない。でも世界で戦うために進めてきた策を、考えるきっかけにはすべきだと思うんですね。ウェルビーイングも、結局1人ひとりが能力を発揮して税金を納めてくれないと国は回らないから。高福祉国家っていいよね、ってよく言われるんですけど、逆に厳しいんです。それで教育にしても何にしても、個人の能力を高めていくことを突き詰めている国だと思うんです。
50歳近くで”転身”する人も少なくない
──前半にあった「フィンランドでは選択の自由度が高く、1つに絞る必要もない」というのは、環境は整えた、あとは皆さんに委ねます、という意味なんですね。
つねに目の前に道が何本もあり、立ち止まっては次に行きたい道を選ぶ。就職も決まった採用時期などないので、自分からアプローチしていかないと何も始まらない。自分は何がしたいか、どうありたいかを真剣に考えないといけないから、決して楽ではないんです。
──実際、就労人口の6割がほかの職場や異分野へ転職している。
違うなと思うとひょひょーいとシフトするんですね。専門性を高めたり新しいスキルを学んだり、資格を取れる講座が地域に安価でたくさん用意されています。“学び直し”の機会が充実していることで、より有意義と思う仕事を目指せる。私の周囲にも50歳近くで保健師に転身したり、農業をやめて薬剤師になった友人がいる。へえー、と驚くんですけど、本人たちはアッサリしたものです(笑)。
駄目ならまたやり直せばいい。安心感とか国への信頼が根底にあるのかな、と思います。年齢・性別にこだわらず勉強し、その結果を認めて当人に任せてくれる社会って、やっぱり成熟してるなと思います。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら









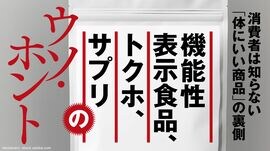











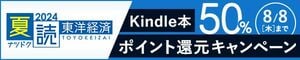
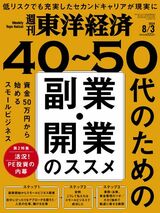









無料会員登録はこちら
ログインはこちら