原作とは異なる一連のエンディングでは、2人の逃避行の末に「こういうことだったのか」と快哉を叫びたくなるような展開が用意されている。塔子が、罪も背負う覚悟で選択した結末とは。ヒントは、塔子と鞍田が共有する記憶に浮かぶ「約束の地」だ。
原作が2014年の作品であったことを考えると、この映画の結末はとても2020年的であると言えるかもしれない。そう感想を告げると、三島は「いまの時代に投げるならこの姿だろうな、というのは明確にありました」とうなずいた。「自分を殺していた人生から、塔子が初めて自分を生き始めた瞬間です。よかった、やっと彼女は生き始めたなと私は思うんですよね」。
あなたの『Red』は?
映画の中で専業主婦から社会「復帰」した塔子は、だんだん色数の多い服を身に着け、自分でも気づかない色を見せていく。鞍田と出会い、仕事の現場という居場所が増えたことで、「塔子の新しい扉が1つ開き、世界がもう1つ始まるんです」(三島)。クライマックスとなる大雪の夜には、白い雪の上に千切れた赤い布が落ちるという象徴的な描写もあり、タイトルの『Red』とは、女の体温を上げ、欲望を刺激し、変化を促し、ここではないどこかへと導く何かを表しているのかもしれない。
「最終的には、見た人が自分の『Red』を感じてくれればいいなと思います。いま、自分で考える前に人やネットに聞いて、漠然とした”みんな”の言うことが正しく思えてしまうような、自分の尺度を持たず尺度が外にある人がたくさんいるように感じて。尺度とは、すべての物差し。ネットでここがおいしいと言われている、じゃなくて、自分の直感で選んでみておいしい体験をする、すべて尺度を1回自分に戻す必要があるんじゃないかと、よく思っているんですよね。
自分の尺度を手に入れるには経験と想像力と選択の覚悟が求められていて、例えば服を選ぶときに、それのどこに自分はいいと思ったのか、なぜ自分はそれを選んでいるのか、理由を明確にしていると好きや嫌い、快不快の自分の物差しが作られていくのかなと思います」

三島は、余貴美子演じる塔子の母に、かつて自分が先輩女性から投げかけられた「どれだけほれて、死んでいけるかじゃないの?」との言葉を言わせ、物語の途中で観客の胸を貫く鋭いシーンを生んでいる。「私たちはそんなにたやすく強くほれるものではないけれど、それでもほれるとき、いろいろなことが一斉に豊かになるでしょう。ほれることのできたときをどれだけ大事にしていくかが、人生を豊かにするような気がします」。
「自分の尺度」を胸に、33歳で誰もが知る巨大な組織をあとにして大きなキャリア転換を図った三島の『Red』は、映画そのものだったのだろうか。では、私の、あるいはあなたの『Red』は何だろう。いま好きな人がいる女もいない女も、好きなことがある女もない女も、『Red』で新しい自分が見えてくるかもしれない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

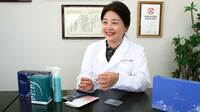





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら