スノーデンが東京で下した大量監視告発の決断 米国諜報機関にいた彼は何を突き止めたのか
この事実から、メタデータは何やら通信の中身に対する直接的な窓ではないという各種の政府の主張はすべて叩き潰せる。世界中でめまいがするほどのデジタル通信が行われている中、あらゆる電話の通話内容が聞かれたり、すべてのメールが読まれたりするなどということは絶対にあり得ない。それができたとしても、大して役には立たないし、そしてどのみちメタデータが仕分けをしてくれるから中身を読むまでもない。だからこそ、メタデータを何やら無害な抽象化だとは考えず、コンテンツのまさに本質だと考えるほうがよいわけだ。それは人を監視する連中が必要とする最初の情報なのだから。
またもう1つある。コンテンツは通常、その人が知っていて生み出すものだと思われている。通話で自分の言うことはわかっているし、メールで何を書いているかもわかる。でも自分の生み出すメタデータはほとんどコントロールできない。というのもそれは自動的に生み出されるからだ。それを集めるのも、保存するのも、分析するのも機械なのと同じく、それを作るのも機械だし、しかも人が介在するどころか、同意することもなしに作り出される。
各種デバイスは、こちらが望もうと望むまいと、絶えずその人になり代わって通信している。そして自分の意志でやりとりを行う人間たちとはちがい、デバイスは中身をわかりにくくするために私的な情報を控えたり、符牒を使ったりはしない。単に最寄りの携帯電話の通信アンテナに、決してウソをつかない信号でピングを送るだけだ。
活動記録のほうが重要
ここでの大きな皮肉の1つは、常に技術イノベーションから少なくとも1世代は遅れる法律が、通信のメタデータよりも内容にはるかに大きな保護を提供しているという点だ──ところが諜報機関はメタデータのほうにはるかに興味がある──データを大量に分析するための「大きな状況」を捉えられるようにしてくれるし、個別の人間の生活についての完全な地図、行動記録、それに関連するシノプシスを作れるようにしてくれる「小さな状況」も可能にする。活動記録のほうが重要なのだ。
そこから彼らは行動の予測を抽出する。要するに、メタデータは監視者に、その人物について知りたいこと、知るべきことをほぼすべて告げてしまう。わからないのは、その人の頭の中で実際に何が行われているのかということだけだ。
この機密報告書を読んでから数週間というもの、いや数カ月にもわたり、ぼくは呆然としていた。悲しく、落ち込み、考え感じることすべてを否定しようとしていた──日本滞在の最後の頃にぼくの脳内で起こっていたのはそういうことだ。
故郷からはるか遠くにいるのに見張られているように感じた。これ以上ないほど成長したように感じつつ、あらゆる人が何か子供じみたものに還元されてしまい、残りの生涯を遍在する親の監督下で暮らすよう強いられているという知識に苛まれた。自分の不機嫌さをリンジーにあれこれ弁解すると詐欺師のような気分になった。
本格的な技術能力を持っているはずなのに、何やらこのシステムの不可欠な要素構築を、目的も知らずに構築支援してしまった自分が大バカ者に思えた。ICの職員として、自分が守ってきたのが国ではなく国家だったことにいまやっと気がついて、利用されたような気分だった。そして何よりも、侵害された気分だった。日本にいるため、この裏切りの感覚は強化されるばかりだった。
それは次回に説明しよう。
(後編に続く)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

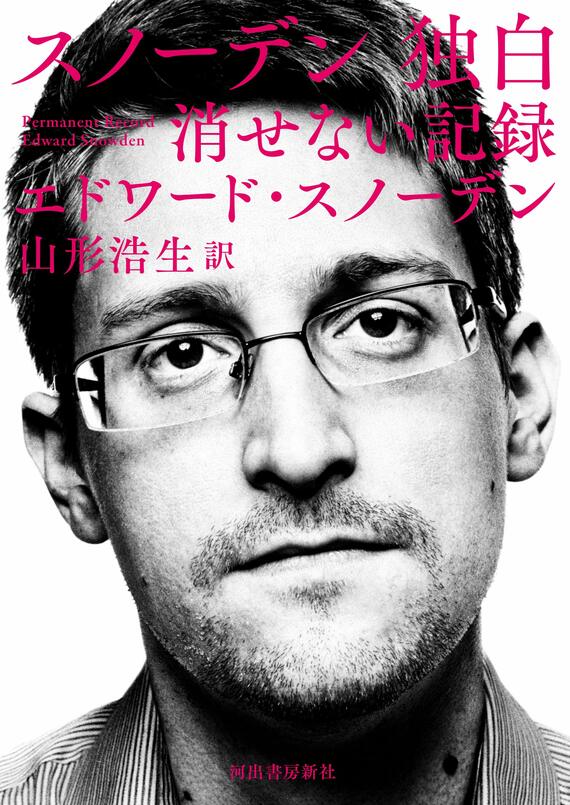
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら