西欧優位の起源となった「世界史の大分岐点」 気候変動と生態環境で見るアジア史
イギリスはいわゆる「危機」に対処するなかで、銃火器の採用とそれに応じた軍隊の革新・軍事革命を達成し、「財政軍事国家」を形成しました。新しい軍隊の維持運営にかかる膨大な費用をまかなうため、財政が巨大化した国家を形成したのです。
それにとどまりません。「財政軍事国家」は民間の経済発展をも促し、加えて科学革命による技術革新を活用して、産業革命が成就しました。
アメリカも単なる銀の供給地ではなくなってきます。アフリカから黒人奴隷を北米大陸や西インド諸島に運び、そこで収穫した綿花や砂糖などをヨーロッパに運び、ヨーロッパから鉄砲や綿布などをアフリカに持ち込む三角貿易です。イギリスはこの貿易でアジア物産購入の費用を捻出したわけで、グローバルな世界経済はすでに形成されています。
やがて軍事革命による植民地征服と産業革命による工業製品輸出で、アジア貿易も黒字に転じました。19世紀は西洋の世界制覇の時代となります。
近代西洋史観と現代
以後の近代史・世界史は、世界の西洋化であって、現代のわれわれにも直結する歴史です。「17世紀の危機」を含む地球の寒冷化が、その出発点に位置していました。
産業革命以後、機械制工業と化石燃料の利用が普及し、それは今も続いているので、気候変動が及ぼした歴史的な影響は、われわれには感知しにくくなりました。
季節・気温の変化にともなう生態環境の条件、それがもたらす生産・流通のサイクル、社会のありよう、いずれもそうです。
そもそも科学革命から産業革命におよぶ近代化とは、ヨーロッパによる自然征服・寒冷化克服のプロセスでしたから、当然かもしれません。
近代の欧米が世界を制覇したことで、その制度・ルール・観念がグローバル・スタンダードになり、今日に至っています。
そのため「世界史」といえば近代西洋史観が中心になり、アジアがヨーロッパの「ネガティブ形態」としてしか捉えられなくなりました。気候変動と生態環境に応じてアジアが築いてきた多くの史実は、現代人が理解しがたいものになってしまったのです。
イタリア・ルネサンスが西洋近代の源流だとしますと、それはアジア史の分派ですので、西洋をみるにあたっても、アジア史に対する正確な理解が必要になるはずです。しかし現代の西洋中心史観では、必ずしもそうはなっていません。
以上に見てきたとおり、アジア史は軍事・経済・政治の各セクターをそれぞれ異なる種族・集団が担うシステムをとっていました。互いに異なる言語・習俗・技能でまとまった遊牧民・商業民・農耕民が、たがいに分業しつつ、提携していたのがアジアだったと言えます。
気候変動に左右される生態環境から、多元的・複合的な制度を導入し、多種多様な集団が共存できる体制を作り上げてきたのです。
それに対して、近代の欧米は国民国家をスタンダードにしているので、均質一体化の体制が前提です。アジア史で通例の多元性・複合性が欠如していて、その欠如した構造を自明の前提として、現代の歴史学・社会科学が組み立てられています。最新の「グローバル・ヒストリー」でも、アジア史・世界史が十全に理解できないゆえんです。
現代の新興国の台頭に対しても、こうした視点は重要だと思います。いわゆる新興国は、中国にせよインドにせよ、かつてアジア史を構成してきた国家です。
西洋化・近代化を経たといえ、その基盤には歴史的な多元的・複合的な体制があるはずで、そこを見誤らないことが変転常ない現代世界に向き合うのに不可欠ではないでしょうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


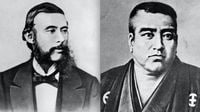
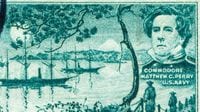



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら