振り返って私たちの暮らしはどうだろう。つねに他者からの評価に晒されている。会社でもそう。日常生活でもそう。「いいね」を獲得するために心をすり減らし、疲弊している人があまりにも多い。
人の目を気にし、顔色をうかがい、自分本来の姿で今を生きているのかさえもわからなくなる。ストレスは日々増大し、心は緊張しっぱなし。それでもお金を得るために、すごいねと言ってもらうために、悩みながらも頑張り続けるしかない。
対して縄文人には生きることへの迷いがない。そんな悠長なことは言っていられない現実が目の前にあるのだ。とにかく懸命に日々を暮らすしかない。
たったそれだけのことなのに、今の私たちにはとても難しい。生きている実感が薄く、それを埋め合わせようと「いいね」を求める。これは、ある意味でのユートピアがもたらした弊害とも言える。
漫然とした日々を過ごす私たちから見ると
ところがホモ・サピエンスは誕生したときから、そんな生温い環境で生きてきていない。つねに想像を絶する厳しい環境の中で生きることと向き合い、拡大してきた。そのDNAを私たちは持っている。
だからだろうか。漫然とした日々を過ごす私たちから見ると、縄文人たちは何と力強く生きているのかと感動すら覚える。人間というのは、本来、こういう生き物だったはずだと。
縄文時代の遺物の中に新たな美を見いだし「縄文の発見者」といわれる岡本太郎。彼は縄文土器に触れたときの感動を著作の中でこう記述した。「たんに日本、そして民族にたいしてだけでなく、もっと根源的な、人間にたいする感動と信頼感(略)」(『日本の伝統』岡本太郎 光文社・知恵の森文庫)。
彼が感じたように、この夏、縄文時代の遺物を目にして、その存在に触れた多くの人の心が揺さぶられた。人間とは何なのか。生きるとはどういうことなのか。私たちが忘れてしまったモノが、縄文人の中にあるのかもしれないと、一種の希望を見いだそうとしているのかもしれない。
次回からはそんな彼らの暮らしをひもといてみたい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


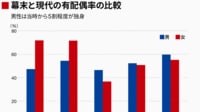





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら