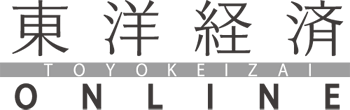ダメ新人から超一流シェフに成った男の半生 世界有数のミシュラン星付き店で輝く日本人
例えば、「カリフラワーを毎回同じ大きさに切れる」といったようなことの方が、よっぽど大事なことだと思うんです。私自身、今でも心のどこかにある、自分の「器用でお調子者」な部分を常に警戒しています。
「憧れ」のようなものを感じて、とにかく追ってみることも必要だと思います。私の場合、それはお店の先輩方が、お客さまとのやり取りの中でイタリア語や英語などを流暢に話す姿でした。ですから、この時期は料理に関する知識のための勉強はもちろん、接客に必要な外国語も勉強していました。それまで自分は勉強が嫌いなんだと思い込んでいましたが、興味さえあれば自らすすんで学べるものだと、この時に実感しましたね。
恵比寿で働いていたこの頃は、右も左も分かっていない自分でしたから、たしかに大変だったと思います。でも、振り返ってみると、こういう時間こそが、今の自分の基礎になっているとわかります。正直「逃げ出したい」と思うことは何度もありましたが(笑)、「辞めたい」と思ったことは一度もありませんでした。それは、料理の現場で学べる喜びの方が圧倒的に多かったからです。「きつい」と感じた時は、常にそう考えていました。
「すべては行動あるのみ」向けられた海外への眼差し
米澤氏:そうして一人前の料理人を目指して少しずつ経験を積んで、ようやく仕事も板についてきた頃、今に繋がる大きな転機が訪れました。すでにホールでの接客を経て、厨房に入っていたのですが、お店が忙しい時は、ホールにかり出されていました。店長は、私が英語も勉強していたことを知っていたので、よく外国人のお客さまの接客担当に指名してくれていたんです。
ある日、アメリカ人の団体のお客さまの接客を担当したのですが、これがきっかけで私の目指す地点がひとつ大きく変化したんです。喜怒哀楽がはっきりとして、リアクションが面白いお客さまに、私も楽しくなって、サービスをさせて頂きましたが、帰り際、私に向かって一斉に拍手してくださったんです。サービスを供する側が逆にサービスを受けてしまったかのような、なんだか不思議な気分になってしまって……。
「なんて素敵な人たちなんだろう。この人たちの住む国アメリカで料理を作ってみたい!」と、この時はじめて、アメリカという国に対して興味が湧いたんです。当時、料理の世界で一流を目指そうと思えば、フランスかイタリアなど、ヨーロッパに留学するのが王道で、「料理でニューヨークへ」というのは一般的ではありませんでした。親を説得し、お店に説明して、とりあえずあるお金でチケットだけは購入して、とにかくできることから動いていました。