「一般党員参加」の実現可能性
国会議員が一人一票を与えられているのに対し、一般党員などの投票は地域ごとにまとめられる。よって、国会議員の投票が重いのは間違いない。だが、小泉総裁の選出時のように大きなブームが起これば、一般党員票が大勢を決することもある。
ただ、実際には規定上定められる一般党員の参加自体が実現しないこともある。たとえば民主党は、代表が任期途中で辞任した場合、後継者を両院議員総会で決めることを例外的に認めており、現在の海江田万里代表もそうして選出された。
実は、民主党で規定どおり選挙が行われたのは2002年と2010年の2回のみで、民主党の代表は実質的には国会議員に選ばれてきたといえる。
最も民主主義的な選出方法を考えるなら、それは一人一票という原則の下、一般党員が国会議員と同じ資格で参加する選挙だろう。日常的に活動を行う党員だけでなく、党費さえ払えば選挙に参加できる、非常にオープンな政党もある。これは、一般社会と隔絶しがちな国会議員の意見にとらわれず、社会の支持を広く探る試みといえる。
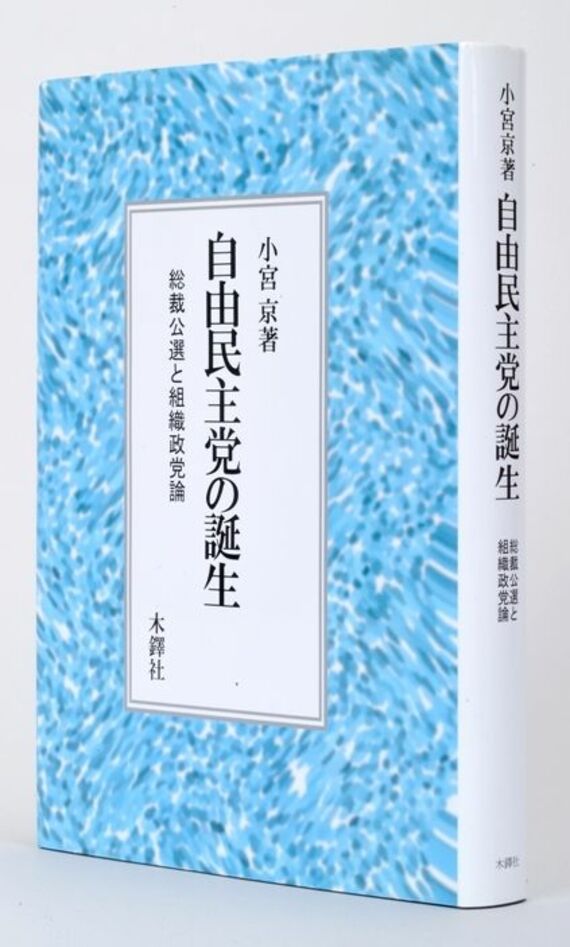
党首選出の比較研究を行った政治学者のウィリアム・クロスらによれば、政党の多くに、限られたメンバーから、議員、一般党員の代表、そして議員・党員を含めた一人一票へと有権者の範囲を広げていく傾向がある。
特に新党や選挙に敗北した政党の、有権者拡大が観察される。また、一つの政党の動きは他の政党に伝播する傾向にあるという。
自民党が長期政権を担っていた時期、選挙の結果はいつもほぼ同じであり、党首選出の方法がダイナミックに変更されることはなかった。しかし、政権交代を経て、政党間の競争は激しくなり、新党も次々に生まれている。
政党の民主性をアピールし、広く支持を拡大するために、国会議員だけでなく、多くの有権者による選挙で党首を決めようとする政党が出現しても不思議ではない。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら