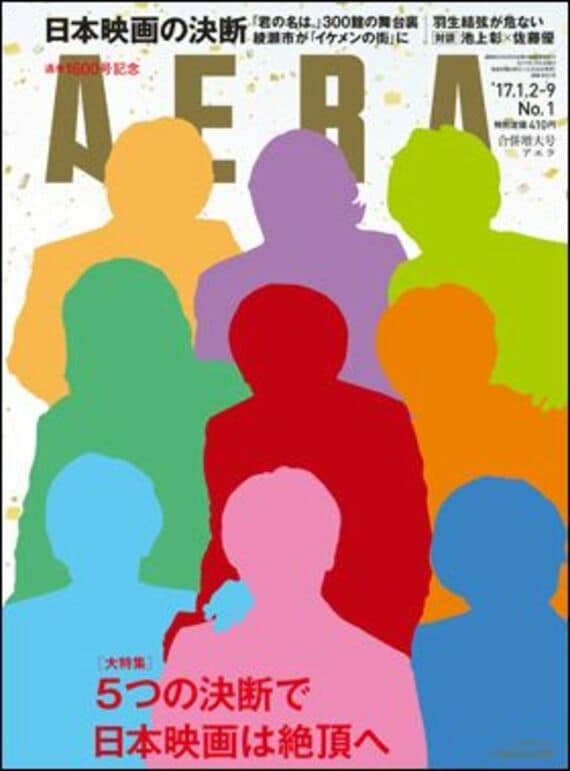監督が儲からない、日本の映画業界への不安 製作委員会よりクラウドファンディング

新人映画監督に贈られる日本映画製作者協会の新藤兼人賞。2016年の授賞式で、映画監督でもある俳優の津川雅彦(76)が乾杯のあいさつに立った。
「日本映画がすばらしいのは、安く作ってもいい作品ができることだ」
とほめた。一方で、こうぶちあげた。
「配給会社は利益を吸い取る。制作側がもうかるわけがない」
絶好調の日本映画だが、手放しで喜べないという関係者は多い。理由の一つが「配給会社だけがもうかる」現状だ。冒頭の式にも出席していたある映画関係者が打ち明ける。
「津川さんの指摘は正しい」
作品によって異なるが、日本では興行収入の5~6割を映画館が持っていき、あとは宣伝費に数億円、残りの3割程度が配給会社に入る。さらに残った分を製作委員会が分け合い、実際に手を動かした制作者の手元には、どんなにヒットしても最初に決めたギャラ以外入らないことが多い。
映画作りには多様性
「誰も知らない」「そして父になる」などを生み出した映画監督の是枝裕和(54)も、こうした現状に危機感を抱く一人だ。
「ヨーロッパでは、監督が映画の著作権者になることが多い。だから権利配分が回ってくる。日本では、アイデアやソフトウェアに対するリスペクトもなければ、そこに対価を払うという発想もなく、『映画がヒットしたら成功報酬をのせてほしい』と制作者が提案しても、なかなか通らない」
日本映画を支えるアニメーション業界も、稼げているのはごく一部。日本アニメーター・演出協会(JAniCA)の15年の調査では、キャリアのスタートとなる「動画」「第二原画」といった職種の平均年収は110万円台だ。人材が定着せず、調査担当者は「予算の配分が下まで回ってこない構造が定着している。産業として成立していない」とまで言った。
制作者に金がまわらないため、作り手は資金力のある大手に限られる。