医学が、「威学」や「脅学」になってしまったことで患者を萎縮させ、「患者の力」を萎えさせてしまう「萎学」になってしまう。この様な例を時々耳にすることがあります。ただ、患者の術後の回復や療養生活のQOL(クオリティー・オブ・ライフ:いのちの質)を考えたとき、これらがいいはずはありません。
患者と医療者が、対立する関係ではなく協働する関係になれば、このような言葉かけはなくなるはずです。それこそが、「市民のための患者学」が目指す医療です。そして、その関係性は、両者が創り上げていかなくてはなりません。
そのためにも、協働作業としての医療の構図を患者さんや市民にも知ってもいたいのです。現実の医療の中で、それが実現しているケースはまだまだ少ないようです。しかし、その構図を知り、お手本が増えてくれば、わが国の医療の中に新しい文化を創ることができると考えています。
“Doctor know best”、すなわち「医師は何でも知っている」時代、医師が医療を独占し、支配する時代は、すでに過ぎ去りました。現代の医療では、医師は看護師や栄養士、薬剤師、放射線技師など周りの医療者の助けを借りなければならないし、それだけではなく、患者と協働する関係を築いて、患者の力を上手く活かし、力づけていかなくてはならないのです。
さて、山口さんの話に戻りましょう。その後の外来でも、山口さんと外科医との戦いは続きました。
外来で、山口さんがリンパ球数を聞くと、「そんな数値、何の役にも立たん。数値なんて、およそ何の役にも立たないもんだ」と返答します。リンパ球数は、免疫力や栄養の指標として有用であり、患者さんが知ろうとすることは、むしろ褒められるべき行為であるとわたしは考えますが、彼はそう考えなかったのです。
その次の外来では、膵臓ガン発見のきっかけになった検査結果の数値がどこに書いてあるのかわからず、独り言を言う山口さんに対して、「腫瘍マーカーの数値などあてになりません。そんなものにとらわれると落とし穴に落っこちますよ。」「あなたは思い込みが激しすぎる」と返答しました。
山口さんが「私、思い込みが激しいですかねぇ?」とやり返すと、外科医は「すごいもんですよ!」と即座に答えます。山口さんは「先生と同じくらい?」と負けずに対話を続けると、外科医は一瞬ドキッとしたらしく、口をつぐみました。
そこで山口さんは、「コウベエ先生と話すのは、この手がいいのかなあ。言われっぱなしにはしないで、2回に1回はソフトに返してみる。そしたら、コウベエ先生とは打ち解けて、話しやすい雰囲気になるかしら?」と、冷静に外科医と意思疎通のできる方法を模索しました。
そして患者は医者のもとを去った
しかし、その後の外来でも、厳しい言葉がけが続きました。「教育者と医療関係者がもっともタチの悪い患者だ。こういう人たちはそろって治る病気も治らなくする人間だ。なまじ医療の本なんかを読んだりして病気にばっかり気が向いているから、治りはしない。再発するんだ。再発して一番慌てるのもあんたのような人ね。もっと、有意義なことに時間を費やしている人は元気でぴんぴんだ」
この4回目の外来診察で、山口さんはこの外科医のもとを離れることを決心しました。



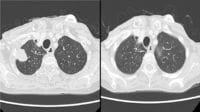





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら