一度きりの死、いかに死んでいけばいいのか 死を考えると生き方が変わる
ステージⅣの末期肺がん患者を、通常の治療のみ、と、それに加えて緩和ケア専門スタッフによる訪問をおこなう、という二つのグループに無作為に分けた臨床研究がそれだ。後者では「患者の状態が悪化したときにスタッフは患者と何を目標とし、何を優先するか」を専門のスタッフと話し合う。その結果「緩和ケアに割り当てられた患者は化学療法を中止するのが早く、ホスピスに入るのもより早く、臨終の際の苦痛がより少なかった」ことがわかった。この結果をどう解釈すべきだろうか。
さらに、驚くべきことに、緩和ケアを受けた患者は、受けなかった患者に比べて、なんと25%も長生きしたのである。まるで画期的な新薬レベルだ。それも安価で手に入れることのできる。
“人は一度きりしか死ねない。死の経験から学ぶことはありえない”
しかし、自ら経験していなくともそのことを良く知っている人に、いかに死んでいったらいいだろうかという困難な問題を相談するのは非常に意味あることなのだ。
こう書いてくると、難しい医学の本なのかと思われるかもしれないが、まったく違う。内容は決して軽くはないが、実際にあった事例の紹介がメインで、医師による訳文もよく、読みやすい本である。著者のアトゥール・ガワンデは、ベストセラー『医師は最善を尽くしているか』で知られ、TIME誌に『世界でもっとも影響力のある100人』に選ばれたこともあるハーバード大学の外科教授だ。
今日を最善にすることがもたらす結果
ガワンデの親族たちのストーリーも紹介されている。父方の祖父は、百歳を超えて主治医に止められても、馬に乗って土地を見回ることをやめない、古き良き時代のインド人であった。たくさんの家族に見守られながら暮らし、バスからの転落事故で亡くなった。妻の祖母は、それとは対照的に、やむなくナーシングホームに入所し、最後の数ヶ月はただ死を待ってみまかった。そして、最も詳しく書かれているのは、インドから米国に渡り、泌尿器科医として名をなした父が、いかにして病と闘ったかについてである。
“今を犠牲にして、未来の時間を稼ぐのではなく、今日を最善にすることを目指して生きることがもたらす結果を私たちは目の当たりにした”
ガワンデの父は、非常に希な、すなわち治療の判断の難しい、脊髄腫瘍に冒される。専門家の意見を聞きつつも自分の医学知識を最大限に活かし、余命を冷静に見つめて自らの生き方を最優先した決断をおこない、死に至るまでの日々を充実して生きた。その経過を間近で見続けたガワンデの言葉がこれである。この本は、父の遺灰をガンジス川に流すところで終わる。
自分でも驚くほど深い感動を覚え、人生観が揺さぶられた。米国では75万部を売り上げたという『Being Mortal』、1人でも多くの人に読んでもらいたいと思っている。みすず書房の本だけあって3千円とやや高めである。しかし、いかに死ぬか、だけでなく、いかに生きるかを教えてくれると思えば、安いものだ。多くの人にこの本を読んでもらえれば、日本の医療が変わる可能性すらあるのではないかと本気で考えている。
翻訳の原井宏明医師による解説はこちら
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

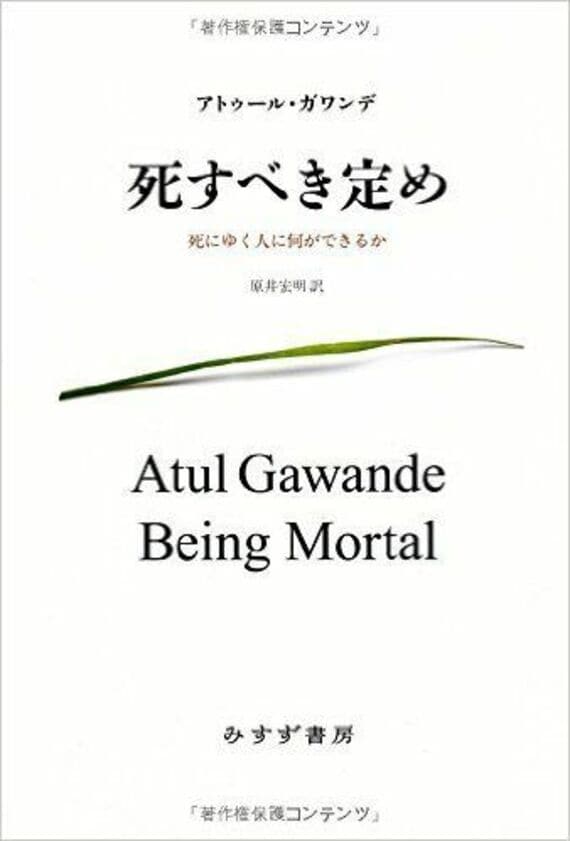

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら