
01. 禁書とは、その時代の政府や宗教的・イデオロギー的権威によって出版や販売を禁止された書物のこと
02. 禁書は日本のみならず世界各国にあり、宗教的や文化的、政治的なタブー、性的な放埓などが理由とされる
03. また魔術の方法を記述したものや占いなど人民をたぶらかすと判断された書物も禁じられることがある
04. 禁書のはじまりは紀元前213年の中国・秦の始皇帝による「焚書坑儒」ともいわれている
05. 焚書坑儒では、秦以前の諸国の歴史書や、一般人が所有する医学・占い・農業以外の書物が焼却された
06. ヨーロッパより早く木版印刷や活字印刷が発達した中国ではその後も歴代王朝が禁書政策を施行している
07. なかでも清朝は輝かしい文化を誇る反面、禁書はことさら厳しく「文字の獄」とも呼ばれている
08. いまも中国では、中国共産党に対する批判や歴史的事件などの書籍は反秩序として違法となる場合がある
09. 国務院直属の新聞出版総署の指示により、各省、自治区、直轄市の出版局がリストを作成
10. 香港以外の中国全土ではその発禁書籍リストをもとに公安関係機関と連携して取り締まりが行なわれている
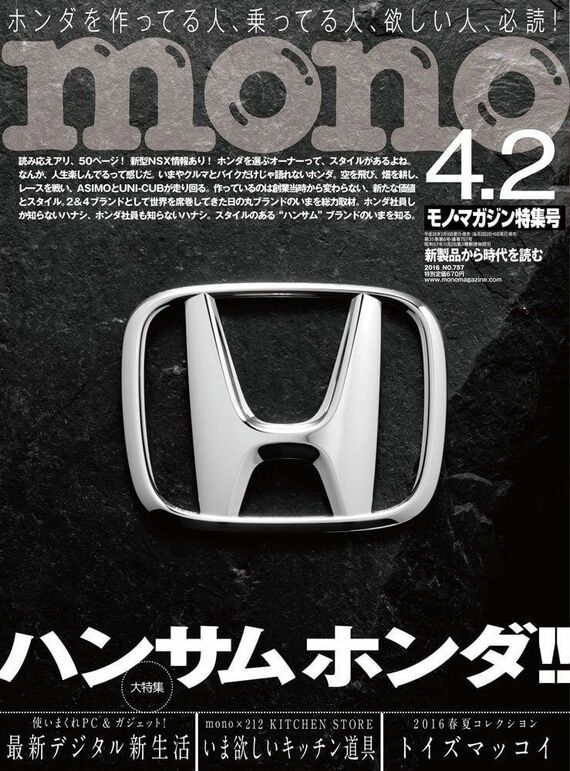
11. 2012年5月上海で起きた違法書籍事件では違法者に5~6年の懲役と罰金、書籍の没収・焼却が命じられた
12. ヨーロッパでは、15世紀に活版印刷がはじまるまで手書きで書物が制作されていたため流通数が少なかった
13. そのため内容のコントロールは比較的容易だったが、印刷物の急増で社会的権威による禁書も盛んになる
14. 中世ヨーロッパでは、ローマカトリック教会が禁書目録を制作し、それは1966年まで続いた
15. アメリカでは青年期の自殺や犯罪を誘発する本をアメリカ図書館協会が有害図書と指定する場合がある
16. 世界における禁書の例はさまざまだが、名作と呼ばれるもののなかにも発売禁止を受けたものが少なくない
発禁になる理由はさまざま
17. 『不思議の国のアリス』は1931年中国・湖南省で擬人化された動物の描写があまりに人間的として発禁
18. 『西部戦線異状なし』はドイツのナチスでドイツ国防軍の栄誉を失墜させ侮辱する描写があるとして禁止に
19. イギリスの作家ジョージ・オーウェルの『動物農場』は反共的テーマを用いたとしてイギリスで発刊遅れ。
20. またドイツでも連合軍に破棄され、1946年には当時のユーゴスラビア、1991年にはケニアで発禁

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら