だいたい松下の本のつくり方は、さすがにこれほどまで執拗ではないが、しかし「異常」であるとは言えるかもしれない。
たいていの場合、自分で思うこと、感じることをPHP研究所の研究員を前にして、数時間、ときには数日にわたって話をする。その松下の話を、ときおり研究員が質問したり確認したりしながら、必ず録音していく。その録音を文字に起こして、ほとんど松下が話したとおりの原稿を作成する。多少話し言葉を書き言葉に変えたり、繰り返しを整理したりする程度である。
その原稿をもとに、いわゆる「勉強会」が始まることになる。所員が声を出して原稿のコピーを読んでいく。松下も片手に鉛筆を持って原稿の字を追いかけていく。読んで、読んで、繰り返し読んでいきながら、必要に応じて「ここは書きかえよう」「ここのところは削除しよう」という指示を出す。その指示は実に微に入り細に入り、われわれ所員がなにもそこまで修正しなくてもと思われるほどの徹底さである。その指示に従って研究員は、同じ作業を繰り返すのである。
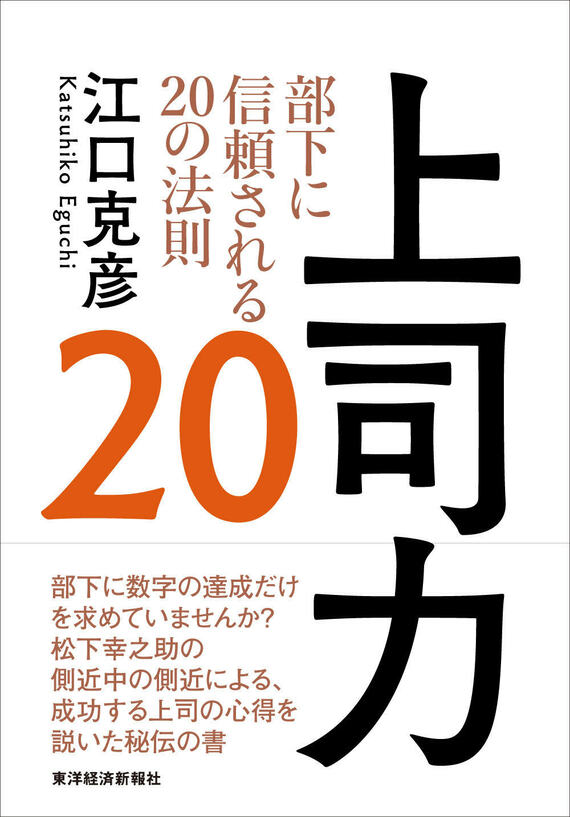
そして、この作業は1、2回で終わることは決してなかった。十数回そういう作業を繰り返しながら、一冊の松下の本がようやくできあがっていくのである。「人間を考える」は100回をはるかに超えている。
そのうえで、いく人かに原稿の感想と意見を求め、さらに修正し、書き直して世に問うのが常であった。したがって1冊の本ができあがるのには、数カ月かかるのが常であったが、なかには数年かかるものもあった。
ことに先の「人間を考える」の原稿は、その修正回数、また意見を聞く人数において、はるかに他の著作をしのぐものであった。半年間にわたる勉強会が終わると、私はいつものように、外部のいろいろな方々の意見、感想を聞き廻るように指示された。有名な識者の方々はもちろん、松下の周辺にいる普通の人たち、幹部の人たちにも意見を聞きに行かされたから、その数は百人以上になる。
多くの人の知恵を集めることの実利
多くの識者の方々がおおむねこの人間観に賛意を示したのに対し、松下の周辺の人たちはどちらかと言えば反対、もしくは批判的であったのが印象に残っている。「世の中とはそういうもの」と松下が言った言葉を、今も印象深く記憶している。
集められた意見は数百にのぼった。松下は、寄せられた意見、感想を一つひとつ丁寧に読み、吟味し、直すべきは直したが、自分が納得しない点については、いかに意見が多くても考えを訂正することはなかった。
しかし、そういう批判、反対の意見はみな、松下の頭の中に入れられていたから、のちに質問を受けたときも、松下は簡単に自説を主張することができて、いわゆる論争に負けるというようなことはなかった。多くの人の知恵を集めることの実利である。
自分の本に対する異常とも思えるほどの執拗さは、言うまでもなく自分の真意を正しく表現したいという思いと、もう一つ、読者の人たちに完璧な責任を果たしたいという松下の信念があったからだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら