日本人が知らない「睡眠大国ドイツ」の常識 平均8時間37分・10年で8分増、睡眠を削るより大事なこととは?
でも、子育ては実質的に「休暇」ではないという声が高まり、2001年に「親時間」(Elternzeit)と名称が変わりました。「親時間」とは、その名の通り、親が子のために使う時間のことです。
親はフルタイムの仕事と同じぐらい、またはそれ以上に、育児に神経や労力を使います。名称が「育児休暇」から「親時間」に変わったことで、かつてドイツでも過小評価されていた「家庭の中の育児労働」が、少しずつ評価されるようになったと思います。
自由な組み合わせが可能な「親時間」
ドイツの親時間は、子供1人当たり最大36カ月取ることができます。取得後は、同じ職場への復帰が法的に保証されており、会社の倒産といった特別な事情を除いて解雇は禁じられています。
「親時間」は、子供が8歳の誕生日を迎えるまで取得可能で、必ずしも生まれてからの数年間ですべて取る必要はありません。ただし、36カ月のうち12カ月は「子供が3歳の誕生日を迎えるまで」に使う必要があります。
つまり、持ち越せるのは最大24カ月。この24カ月分を、3歳から8歳の間に取ることができます。両親が同時に取ってもいいですし、別のタイミングで取得してもかまいませんが、一般的なのは後者です。
例えば、36カ月を両親で平等にわけて「父親も母親も1年半ずつ取得する」ケースもあれば、「子供が生まれてから母親が1年間取得し、父親はそのあとに取る」というケースもあります。
一定の「枠」はあるものの、枠の範囲内では比較的、臨機応変に取得できるため、さまざまな組み合わせがあり、「誰がいつ取得するか」は、本当に人それぞれです。ドイツでは女性の90%以上、男性の40%以上が親時間を利用しています。
ヨヘンさんは、「週に3日仕事をする時短勤務」であるため、フルタイムで働くドイツ人よりも有休の数が少なく、年間18日です。でも有休の数に満足していると言います。というのも、会社が「融通の利く取り方」を許可してくれているからです。
「有休が足りなくなると『時間調整』(Zeitausgleich)で休みを取っているんだ。上司も、これに積極的で、休みについて相談をすると『この日とこの日は時間調整にしたら?』なんて言ってくれるからありがたい」
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

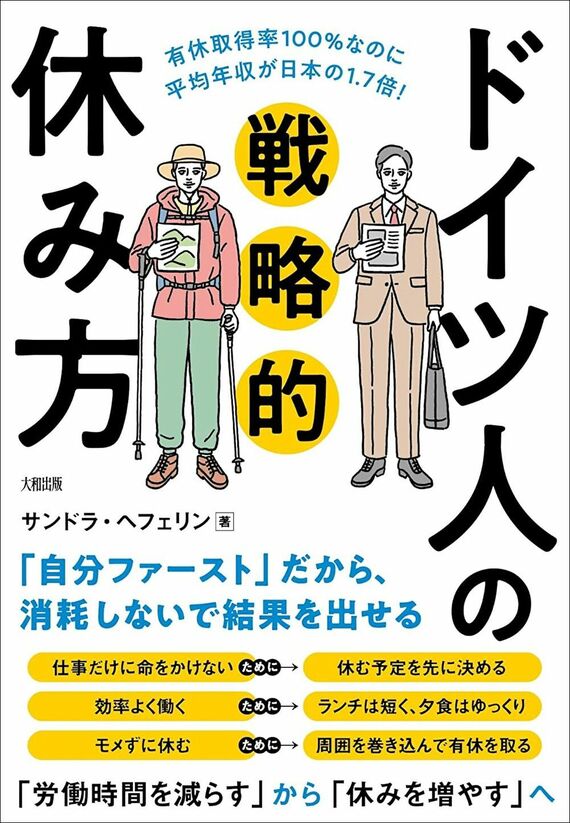































無料会員登録はこちら
ログインはこちら