「これは妻に相談だ!」 改正が相次ぐ育児休業 社労士が徹底解説する

都内でSE職として働くAさん(35歳)。彼には不妊治療に専念するため退職した妻(33歳)がいます。努力の甲斐あって子を授かり、この春に安定期に入りました。
Aさんが部長に報告するとすぐに人事面談が組まれ、ぐいぐいと詳細を聞かれます。最後に「奥さんと相談して産後にあわせて育休とれば? およそ1カ月だけど手取り分は給付が出るよ?」と言われました。
「うちは専業主婦だけど……育児休業ってオレが?」
「給付金って給与の半分ぐらいって話じゃ?」
混乱しつつ席に戻ると、育児休業中の女性の後輩とばったり会います。聞けば、人事部へ育児休業延長のお願いかたがた顔を出しに来たとのこと。後輩は、「もう少し子どもといたいし、まあイマドキ延長が当たり前ですしね」と一言。
奥様の出産予定は8月。Aさんはどんな予定を立てるでしょうか。
1.相次ぐ育児介護休業法の改正
育児介護休業法は施行されて以降頻繁に改正が行われており、この2025年10月にも改正されます。特に2022年以降の
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備のために、研修の実施や相談窓口の設置等の措置を講じる義務
・出生時育児休業制度の創設
・育児休業の分割取得
は会社側の方針を明らかにし、ルールを再構築する必要のある改正でした。




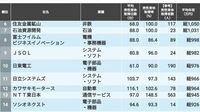



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら