「紀伊・和泉28万石を領有」も秀吉の直臣には手出しができず…羽柴秀長の【意外に窮屈】な領国支配
それらの所領には、秀吉から「守護不入」の特権が与えられる場合がみられ、その場合には、秀長の領国支配権はおよばなかった。
初期徳川政権の「国奉行」制に通じる性格
その一方で、秀長は領国統治者として、各浦への船徴発にみられる、両国に対する一斉的な公事(租税・負担)を賦課する権限があった。
この場合、「守護不入」所領に対してはどうであったのかは、具体的な史料がないから確定できないが、その船徴発の場合をみると、公事の内容によっては「守護不入」所領にも賦課できた場合があったととらえられる。
したがって秀長の領国支配の性格は、領国一円を排他的に統治するものではなく、政権主宰者の秀吉による関与が存在していたものととらえられる。
こうした性格の領国支配は、例えば戦国大名相模北条家の場合で、「支城領」支配と定義されているものにあたる。またその後の初期徳川政権における「国奉行」制に通じるものとみなされるだろう。
もっとも羽柴(豊臣)政権、続く徳川政権(江戸幕府)においても、政権による領国支配への関与が全くみられなかった、外様大大名による領国支配も存在していた。その領国統治の性格は「自分仕置権」と定義されている。
それと比べると秀長の領国支配は、あくまでも政権の管轄下に位置付けられたものととらえられる。
羽柴政権においては、一門衆の領国支配は、完全に自立したものではなく、政権による直接的な関与がみられる性格にあった、ととらえられる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

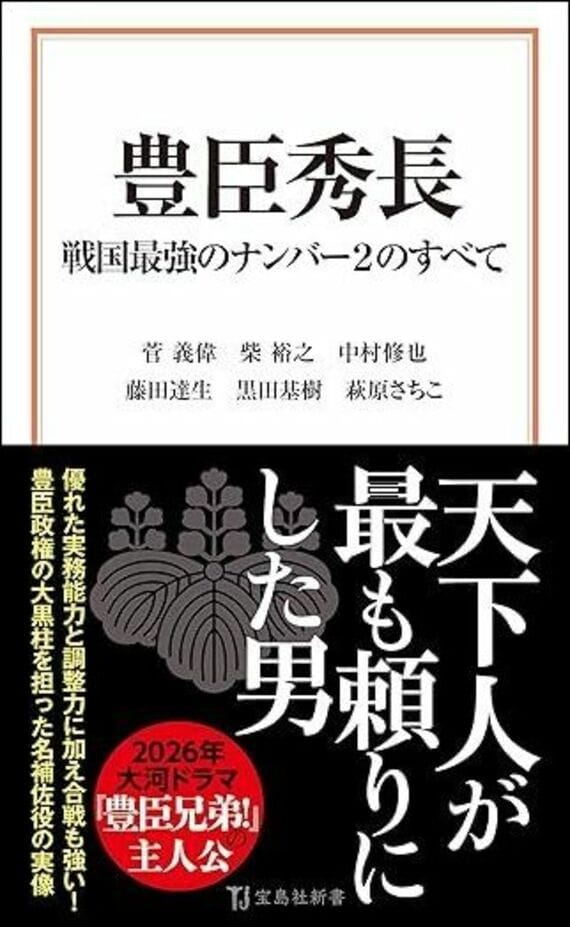































無料会員登録はこちら
ログインはこちら