
ぶっ通しで働いてはならない
勤務間インターバルという言葉は皆さんもちょくちょく耳にするかと思います。
1993年にEU(欧州連合)で発令された労働時間指令をお手本にしたもので、勤務時間インターバルとも呼ばれます。
EU指令は「24時間のうち連続11時間は休養時間をとらなければいけない」というものです。
簡単に言うと、何時間もぶっ通しで働くことを禁じ、一定時間の休憩をはさむよう義務づけています。
こうお話しすると、皆さん「えーっ、ヨーロッパの人はそんなに休んでいるんですか」と驚かれます。
たとえば始業時刻が朝9時の人が、ある日、夜12時まで残業したとしましょう。普段だと、休養時間は翌日の始業時刻9時までの9時間になります。
仮に通勤が往復で2時間、食事や身支度などに1時間かかるとすれば、睡眠時間は6時間しかありません。

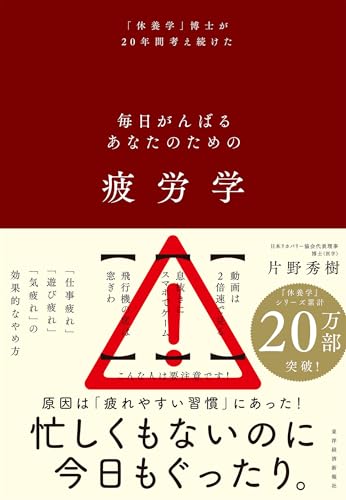
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら