「マムシより危険?」「よくいるヘビだが、過去に死亡事故も」意外な"最恐ヘビ"《ヤマカガシ》の正体…最新研究でわかった"驚きの事実"
そこで『ウェブ画像を用いた研究方法で全国各地の体色を調べたら面白いのではないか』といった話がでてきたんです。それが今回の研究の構想になっています」(福田さん)
研究者による野外での調査のみでは限界があるが、ウェブ検索を使えば画像収集の可能性が広がる。日本列島にいるヤマカガシを調べることができるかもしれない。
こうして2018年に福田さんを中心として「ヤマカガシ体色プロジェクト」が始動。研究は、本業のかたわら、終業後や休日などに進めたという。まるで“自由研究”のような取り組みだ。
メンバーは、東京大学大学院で地球惑星科学を専攻する特任研究員の久保孝太さん、在野研究者の福田文惠さんも加わり4名になった。
ヤマカガシの画像を集めるために、まずウェブ検索と、Google Imagesなどのツールを活用した。しかし画像が見つからない地域も多い。そこでTwitter(現在のX)で画像提供を呼びかけることにした。

全国から「953枚のヘビ写真」が集まった
期間は、2018年4月から2020年6月まで。呼びかけの投稿には、収集の目的や写真の条件、毒ヘビへの注意喚起も添えられている。全国各地から、スマートフォンなどで撮影されたヤマカガシの写真が寄せられた。
これらSNSやウェブ検索における画像収集において、細木さんが注意を払ったのは「バイアス」だ。
「奇怪な色や現象などはSNSで拾いやすく、稀なものがあたかも多く観測されているかのように見えてしまいます。また調査地域が限られてしまうと、それもバイアスになる。寄せられる写真を注意深く精査すること、できるだけ広い地域から多くの写真を得られるようにしました。ウェブ検索での画像収集時は、都道府県ごとに検索時間を決め、バイアスがかからないように工夫しました」(細木さん)
















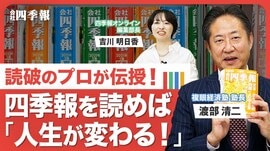















無料会員登録はこちら
ログインはこちら