「マムシより危険?」「よくいるヘビだが、過去に死亡事故も」意外な"最恐ヘビ"《ヤマカガシ》の正体…最新研究でわかった"驚きの事実"
「ヘビを専門としていない立場から見ても、ヤマカガシは非常に面白い対象です。これほどまで日本列島レベルで体色に違いがあるにもかかわらず、その機能はおろか、全貌すらわかっていませんでした。
一方で、江戸時代の博物図譜や浮世絵にもヤマカガシは描かれていて、日本人にとって馴染みがありますよね。そこで市民の力をお借りして色彩多型の全貌を解き明かせるのでは、と考えて研究をスタートしました」(細木さん)
また、基礎的な研究の重要性だけではなく、咬傷事故を防ぐうえでも地域ごとにどのような体色が見られるか、多様性を明らかにし周知することは重要だととらえ、研究を進めた。

メンバーにはヘビに詳しい研究者ももちろんいる。
論文の共筆頭著者であり、京都大学のリサーチ・アドミニストレーター(URA:研究支援専門職)の福田将矢さんは、大学院時代にヤマカガシを研究していた。
専門は動物行動学と生態学で、ヤマカガシがヒキガエルを食べて毒を利用する性質について、野外観察や室内実験、化学生態学者らとの協力のもとで検証した。
「ウェブ画像」に見い出した可能性
今回のプロジェクトでは、体色の分類や論文執筆に加え、市民との連携をはじめとした市民科学パート(SNSやウェブページの運営など)を担当している。
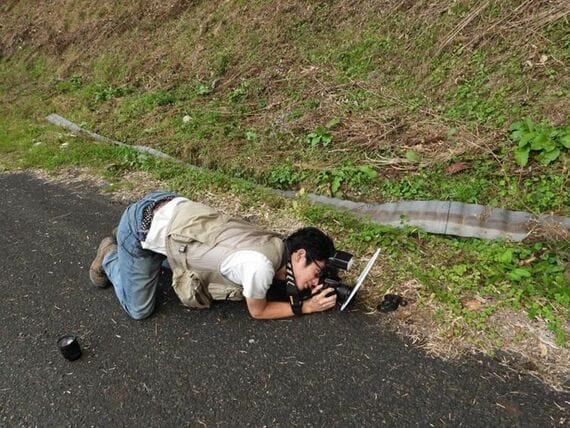
細木さんと福田さんは友人で、大学時代の公開臨海実習で知り合った仲。細木さんの進化生物学、福田さんの動物行動学は分野が近く、お互いの研究について話をしていたという。そんな間柄の会話からプロジェクトは生まれた。
「このプロジェクト自体は大学院時代、細木くんと共通の友人の3人で行った奄美旅行がきっかけです。私がヤマカガシの色彩多型の面白さを語ったとき、細木くんは赤くないヤマカガシがいることに大変驚いていました。
















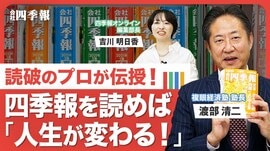















無料会員登録はこちら
ログインはこちら