「マムシより危険?」「よくいるヘビだが、過去に死亡事故も」意外な"最恐ヘビ"《ヤマカガシ》の正体…最新研究でわかった"驚きの事実"
※記事中盤以降に、「地域別のヤマカガシの特徴」と写真が出てきます。苦手な方はご注意ください。
2025年5月、ヤマカガシの色彩変異を明らかにした論文が、1856年創刊のイギリスの動物学雑誌『Zoological Journal of Linnean Society』に掲載された。
北海道大学や京都大学の研究者4人がヤマカガシの色彩多型に着目し、「ヤマカガシ体色プロジェクト」を始動。市民160人の協力を得て日本列島スケールで調査・分析を行い、「123」もの色柄のパターンがあることを発表した。
実は、ヤマカガシの体色自体は、半世紀以上前から研究されてきた。
1970年代以降の記載研究(※1)によると、ヤマカガシは「関東型」「関西型」「九州型」「青色型」「白黒型」「黒化型」と大まかに6種あることがわかっていた(※2)。
一方で、研究者やヘビ好きの間では「さらに多様な色柄の存在」がささやかれていた。そして今回、日本列島全域におよぶプロジェクトによって、複雑な色彩パターンが示されたのである。

限られた観測はバイアスを生み、誤った結論に達することもある。実際、ヤマカガシの色彩多型の研究が行われたのは限られた地域のみであった。今回挑んだのは日本列島全域におよぶ。
どのように全国規模でヘビを調べたのか。そもそもなぜ今、ヤマカガシなのか。研究者に話を聞くと、ユニークな研究背景と真摯な目的が見えてきた。
その機能はおろか、全貌すらわかっていない
「実は私、ヘビはまったくの専門外なんです」
そう語るのは、研究メンバーで論文の筆頭著者である北海道大学北方生物圏フィールド科学センターJ-PEAKS事業 特任助教の細木拓也さんだ。
専門は「進化生物学」で、「種がいかに生まれ、維持され、消失するのか」を野外観測と集団遺伝学、実験進化を用いて検証している。
実験生物はトゲウオやサクラマスなどの魚類で、ヘビは研究の対象ではない。「ヤマカガシ体色プロジェクト」では、研究デザイン、ウェブ上からの画像収集と統計解析、論文執筆を担当した。

















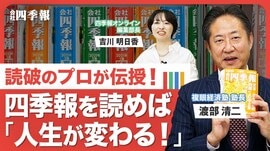















無料会員登録はこちら
ログインはこちら