「吉沢亮や横浜流星の好演だけじゃない」映画『国宝』の超ヒットを導いた《李相日監督の“背景”》
同作は、李監督自身と同じく、在日朝鮮人で朝鮮学校に通う野球部の青年2人を中心とした物語。これまで朝鮮学校が参加できなかった、甲子園をはじめとした公式戦に参加できることになったということから物語が動き始める。

『国宝』と李監督デビュー作に通じる「血」
彼らが日本人に差別されている――といった単面的な話ではなく、日本人とは結婚させないと豪語する両親や、「仲間意識が強すぎて絶対に外のものを受け付けない。いつも自分たちの狭い世界だけでものを考えている」とする朝鮮学校の閉鎖性なども描かれる多層的な作品だ。
ラストは男子高校生同士に冗談交じりに「やめたいか、朝鮮人?」と会話をさせ、主人公が「なっちまったもんはしょうがねえからな⋯⋯俺は俺だ」と言って終わるなど、変えられないものを背負う彼らの生き方を爽やかに描く、若き李監督の大いなる才能を感じさせる傑作だ。
そう、主人公が自分に流れる血と向き合うという点は、くしくも『国宝』が内包するテーマと通底するものがある。
「なっちまったもんはしょうがねえ」と自分に流れる血を受け入れるシーンは、『国宝』で喜久雄が俊介に「血が欲しい」と語りかけるシーンと対をなしているようにすら思える。
さらに言えば、男性2人の友情物語である点や、別の血が流れる人間がこれまで参加できなかったはずの世界に加わって新しい世界が見えてくるという設定、同じ血であることにこだわって排他的になる人たちもいるといった描写にまで、通じるものがある。
『青〜chong〜』から四半世紀。実は『国宝』は李監督がデビュー作で向き合った根源的なテーマに原点回帰するような題材なのだ。
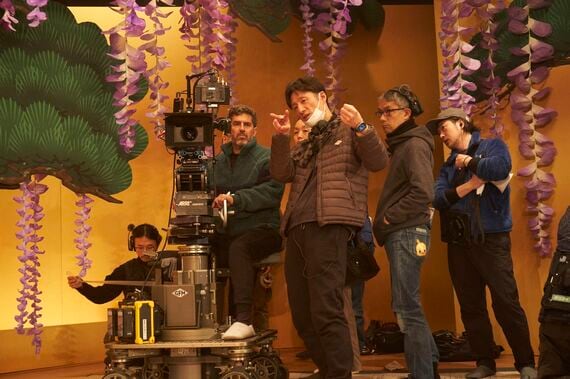
抱えるテーマとしては通底しているが、『国宝』に関しては、李監督は当事者=歌舞伎界の人間ではないからこそ、描き方には一定の距離があり、肩入れしすぎていない。その適度な距離感が、歌舞伎のファンだけではない、より広い層の観客に届いたとも考えられる。
原作者とのタッグ、演出手法など、『国宝』は李相日が、自身で積み上げてきたキャリアの上に、根源的に抱えるテーマが重なったからこそ撮れたといっていい、原点回帰であり集大成のような作品なのである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら