Z世代の「就活も母と一緒に」は、甘えているわけではない⁉ 彼女たちが従来の母親以上に“優秀なメンター”なワケ
博報堂生活総研は、わが子に並走したり先回りしたりしてサポートする母親を「メンター・ママ」と呼びます。同主任研究員の酒井崇匡氏いわく、「Z世代の母親は、それ以前の世代より共働き比率が高く、母親が一社会人としても、わが子に信頼や尊敬をされている部分があるのでは」と言います。確かにその通りでしょう。
頼れる母親「メンター・ママ」が増えた
Z世代の母親の中心は、真性バブル世代と団塊ジュニア。彼女たちの多くは、女性の高学歴化、共働き化が進む1990年代半ば前後に、大学進学や就職を経験してきました。
女性の短大進学率と四年制大学への進学率が逆転したのは1996年、また専業主婦世帯と共働き世帯が逆転したのも1996年。つまり、彼女たちの進学や就職、結婚の前後の時期に、時代が大きく動いたのです(2019年 内閣府「男女共同参画白書」)。
また、真性バブル世代は「均等法(男女雇用機会均等法/1986年施行)」の第1世代で、バリバリ働く「バリキャリ」志向が強かったのに対し、団塊ジュニアは1990年代後半の「労働者派遣法改正」を機に、派遣社員に転じた割合も高いとされます。
それでも2024年時点で、団塊ジュニアを中心とした45〜54歳(含・有配偶)女性の8割強(80.9%)が働いているほか、同年代の既婚女性に限っても、「夫婦共にフルタイム就業」が、2019年時点で同世代女性の約4組に1組(約25%)にのぼっていました(総務省「労働力調査」ほか)。
フルタイムやそれに近い状態で働いていれば、さまざまな角度から仕事関連の情報が入ってきやすく、優秀なメンターにもなりやすい。実際に博報堂生活総研が、Z世代の一部(19〜22歳/男女)に聞いた調査でも、頼れる母親の増加が見てとれます。
具体的には、「悩みごとを一番相談する相手は母親」や、「母親からのアドバイスや忠告の通り行動することが多い」との回答が、30年前(1994年)と2024年の比較で、20ポイント前後も増えました(10.5%→31.8%/51.5%→68.0%)(「若者30年変化」)。
つまり、Z世代が「母親に甘えている」から親子就活が増えたというより、昭和の時代以上に「頼れる母親」だからこそ、就活を共にするようになった側面もあるはずです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

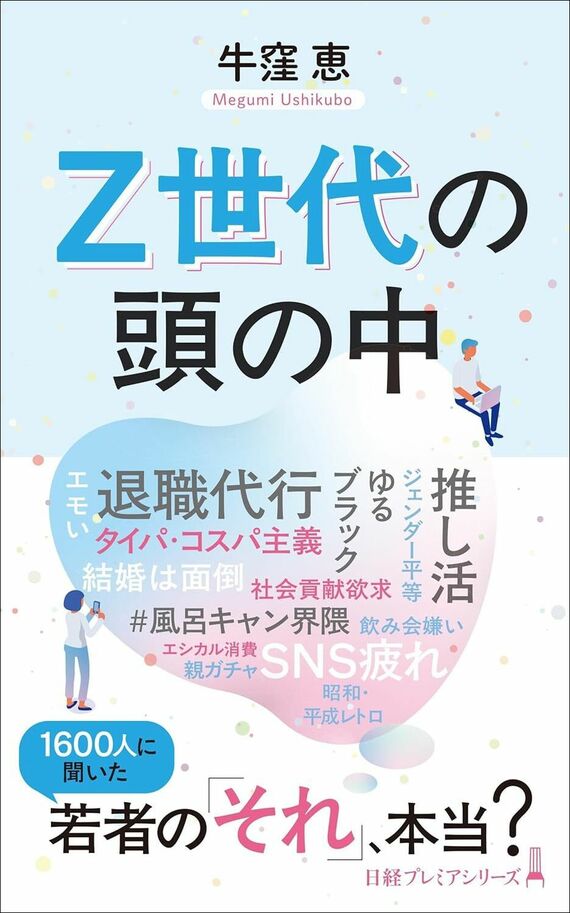






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら