
「報連相」はビジネスマン必須のスキル?
社会人必須のビジネススキルとされる「報連相(ほうれんそう)」。広く提唱されて40年以上経つ今日でも、日本企業のほとんどは「報連相ができる人材がほしい」と語り、社員研修でも基本中の基本として必ず教育される。だが正直なところ、「報連相しろって言われても、具体的に何をすればいいのか分からない」と内心疑問を感じている人は多いのではないだろうか。
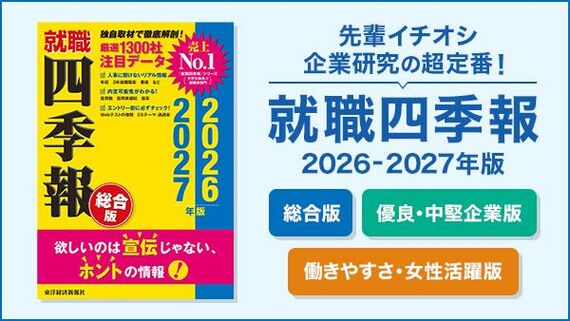
筆者は長く若手人材の就業支援に携わり、現在はウズウズカレッジという会社でIT分野の転職支援やリスキリング(学習)支援、法人研修を提供している。さまざまな企業から人材育成について課題をヒアリングすることも多いのだが、常々感じるのが「報連相を求めているが、その定義はバラバラ」で、それによって「報連相ができない社員」を量産する状況に陥っているということだ。
前回の記事「長時間働く人はえらい?『労働生産性』が低い日本で"努力の美化"が組織をダメにする理由と脱却への3ステップ」にも書いたが、日本企業は少子高齢化による労働力の減少、賃金上昇圧力、国際競争の激化といった社会的課題に直面している。
この状況を切り抜けるには「限られた人員で成果を最大化する」ことが必須だが、定義や目的が曖昧な報連相を教育することは、無駄なコミュニケーションを現場に強いてしまい、業務効率化を妨げる要因になりかねない。語呂が良いだけで生き残ったんじゃないかという「報連相」というビジネスマナー。具体的に「何のために」「いつ」「何をすればいいのか」を明確にしないと、このまま「使えないビジネスマナー」として長生きし続けるだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら